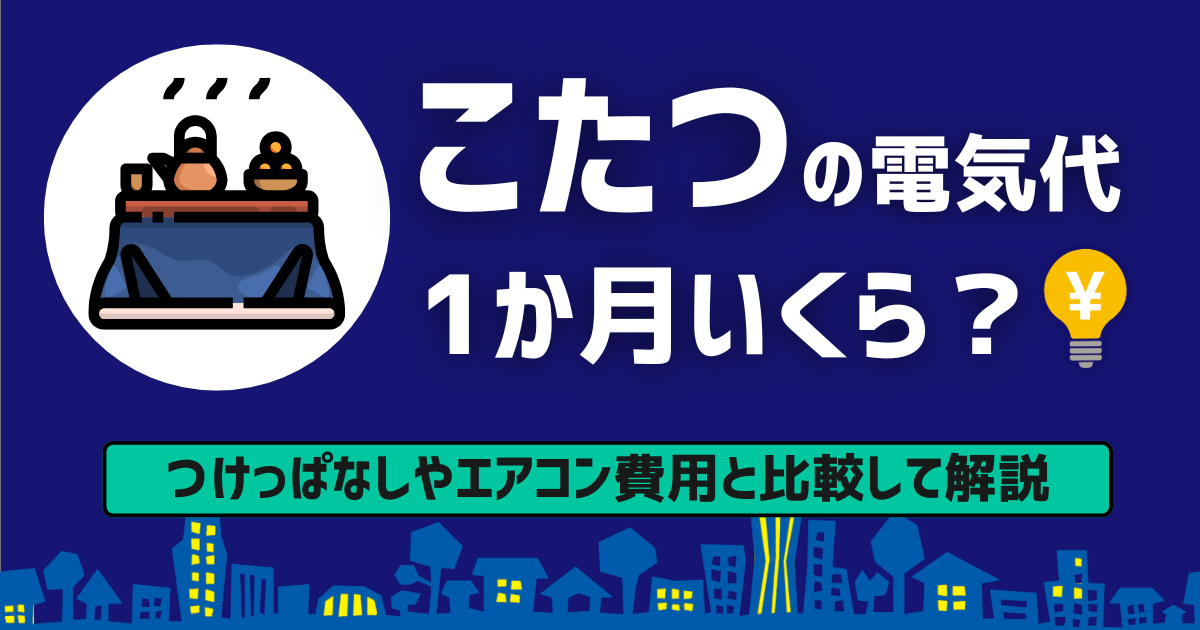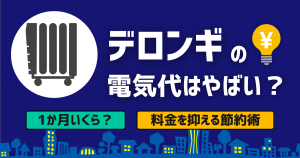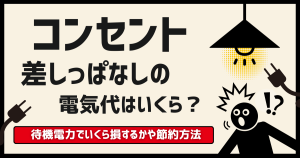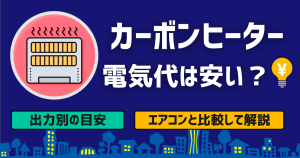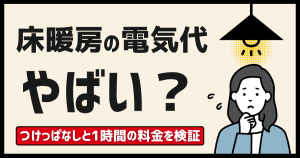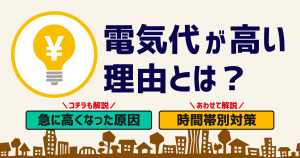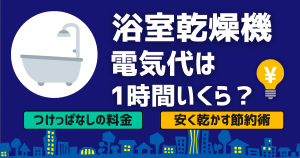冬の暮らしに欠かせないこたつは、手軽で心地よい暖房器具として人気です。
しかし、つけっぱなしにすると電気代はいくらになるのか、エアコンと比べて本当にお得なのかといった具体的な費用について、疑問を持つ方も少なくありません。
こたつの電気代はほかの暖房器具より安い傾向にありますが、使い方や電力契約によっては思ったほど節約できないケースもあります。
本記事では、こたつの電気代の具体的な計算方法から、効果的な節約術、そして電気代を根本から見直す方法までを網羅的に解説します。
暖房費を賢く節約したい方は、ぜひ参考にしてください。
【結論】こたつの電気代は1か月約1,000円から!つけっぱなしでも工夫次第で安くできる

冬の暖房器具として人気のこたつですが「実際の電気代はいくらかかるのだろう、つけっぱなしにすると高くなるのでは」と疑問に思う方もいるでしょう。
こたつの電気代は、使い方を少し工夫するだけで、想定以上にお得に利用できる可能性があります。
本章では、こたつの具体的な電気代について、次の3つのポイントから詳しく解説します。
こたつの電気代の目安
- 1時間あたりの電気代の計算方法と具体的な目安
- 1日つけっぱなしの場合の電気代シミュレーション
- 1か月使用した場合の電気代モデルケース
それぞれの内容を具体的に解説します。
1時間あたりの電気代の計算方法と具体的な目安
こたつの電気代は、簡単な計算式で自身でも算出が可能です。
電気代は、消費電力(kW) × 使用時間(h) × 1kWhあたりの電力量料金単価(円)で求められます。
消費電力はこたつの説明書などで確認できますが、ここでは一般的な目安として「弱」で100W、「強」で200Wとして計算します。
また、1kWhあたりの電力量料金単価は、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が示す目安単価の31円(税込)を使用します。
1時間あたりの電気代の計算例
- 設定「弱」の場合:0.1kW × 1時間 × 31円/kWh = 3.1円
- 設定「強」の場合:0.2kW × 1時間 × 31円/kWh = 6.2円
このように、こたつの1時間あたりの電気代は、設定が「弱」であれば約3.1円、「強」でも約6.2円と、非常に経済的であることがわかります。

1日つけっぱなしの場合の電気代シミュレーション
こたつを24時間つけっぱなしにした場合の電気代は、先ほどの1時間あたりの電気代を基に計算できます。
仮に24時間ずっと同じ設定で使い続けたとすると、電気代は次のようになります。
24時間つけっぱなしの場合の電気代
- 設定「弱」の場合:3.1円 × 24時間 = 74.4円
- 設定「強」の場合:6.2円 × 24時間 = 148.8円
もちろん、実際にはこたつ内部の温度を一定に保つサーモスタット機能が働き、常に最大出力で稼働しているわけではないため、上記の金額よりも安くなることがほとんどです。
しかし、このシミュレーション結果からも、設定温度を「強」から「弱」に変えるだけで、電気代に大きな差が出ることがわかるでしょう。
1か月使用した場合の電気代モデルケース
それでは、より現実に近い形で1か月あたりの電気代をシミュレーションしてみましょう。
本章では、1日に8時間、設定を「弱」にして30日間使用したというモデルケースで計算します。
計算式は、3.1円(1時間あたりの電気代) × 8時間 × 30日間となり、合計は744円です。
もちろん、家庭の人数やライフスタイルによって使用時間は変動しますが、標準的な使い方であれば、こたつの電気代は1か月あたり1,000円前後に収まることが多いと考えられます。
総務省の家計調査によると、二人以上世帯の冬場(2025年 1月〜3月)の平均的な電気代は1か月で約10,000円〜約22,000円です。
このことからも、こたつがいかに経済的な暖房器具であるかがわかります。
【徹底比較】こたつはほかの主要な暖房器具より電気代が安い傾向

こたつが経済的であることはわかりましたが、エアコンやホットカーペットといったほかの暖房器具と比べるとどうなのでしょうか。
それぞれの電気代を比較することで、自身のライフスタイルに合った、より賢い暖房器具の選び方が見えてきます。
本章では、代表的な暖房器具との比較を通じて、こたつの経済性をさらに掘り下げていきます。
暖房器具の電気代比較
- エアコン(暖房)との電気代比較
- ホットカーペットとの電気代比較
- 電気毛布との電気代比較
- 【目的別】暖房器具の賢い使い分けと組み合わせ方
各暖房器具との違いを詳しく解説します。
エアコン(暖房)との電気代比較
結論からいうと、こたつの方がエアコンよりも電気代は安くなることがほとんどです。
その理由は、それぞれの暖房器具が暖める範囲の違いにあります。
こたつが足元など身体の一部を直接暖める「局所暖房」であるのに対し、エアコンは部屋全体の空気を暖める「全体暖房」です。
そのため、エアコンはこたつよりも多くの電力を消費します。
一般的なエアコンの暖房時における1時間あたりの電気代は、設定温度や部屋の広さ(6畳〜14畳)にもよりますが、約15円〜約40円程度が目安です。
こたつの電気代(約3.1円〜6.2円)と比較すると、その差は明らかでしょう。
経済産業省 資源エネルギー庁の調査でも、家庭における冬の電力消費のうち、暖房が大きな割合を占めることが指摘されています。
部屋全体を暖める必要がない場面では、こたつを積極的に活用することが節約につながるといえます。
出典:経済産業省資源エネルギー庁|省エネ性能カタログ2024年版
出典:経済産業省資源エネルギー庁「家電製品別の電力消費割合を知ろう!」
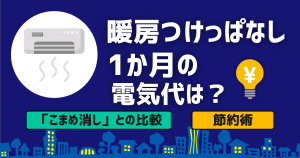
ホットカーペットとの電気代比較
こたつと同じく、床面を暖めるホットカーペットも人気の暖房器具です。
ホットカーペットの電気代は、製品のサイズや設定温度によって異なりますが、2畳用のタイプで1時間あたり約9円〜約10円程度が目安となります。
こたつと比較すると、ホットカーペットの方が電気代はやや高くなる傾向があるといえるでしょう。
これは、ホットカーペットの方が暖める面積が広く、消費電力が大きくなるためです。
ただし、こたつはテーブルの周辺しか暖められないのに対し、ホットカーペットは敷かれている範囲全体を暖められるというメリットがあります。
どちらがよいというわけではなく、暖めたい範囲や用途に応じて選ぶことが大切です。
電気毛布との電気代比較
一人用の暖房器具として、電気毛布も非常に経済的です。
電気毛布の1時間あたりの電気代は、製品にもよりますが約1円〜約2円程度と、こたつよりもさらに安価なケースが多く見られます。
就寝時に布団を暖めたり、ソファでくつろぐ際に体に掛けたりと、ピンポイントで暖を取りたい場合には最適です。
ただし、こたつのように複数人で同時に利用したり、テーブルとして使ったりすることはできません。
暖房器具の中でもとくに電気代を抑えたい場面で活躍する選択肢といえるでしょう。

【目的別】暖房器具の賢い使い分けと組み合わせ方
こたつやエアコン、電気毛布には、それぞれ得意なことと不得意なことがあります。
それぞれの特性を理解し、シーンに応じて使い分けることが、快適さと電気代の節約を両立させる鍵となります。
シーン別の使い分け例
- 一人で短時間過ごす場合:こたつ、または電気毛布
- 家族がリビングに集まる場合:エアコンとこたつを併用
- 床で直接くつろぎたい場合:ホットカーペット
たとえば、一人暮らしの方や、日中に一人で過ごす時間が多い方は、部屋全体を暖めるエアコンよりも、こたつを中心に使う方が効率的です。
一方、家族がリビングに集まる際は、エアコンで部屋全体をほんのり暖めつつ、こたつで足元を十分に暖めるという併用がおすすめです。
エアコンの設定温度を1℃下げるだけでも大きな節約につながるため、こたつとの組み合わせは非常に効果的といえるでしょう。
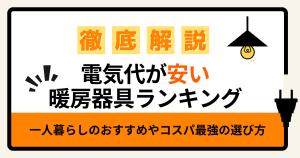
【今日からできる】こたつの電気代を抑える効果的な5つの節約術

こたつはもともと経済的な暖房器具ですが、さらに使い方を工夫することで、電気代を効果的に節約することが可能です。
少しの心がけで、冬の電気代に差がつくかもしれません。
本章では、今日からすぐに実践できる、こたつの電気代を抑えるための具体的な方法を5つのポイントから紹介します。
こたつの節約術
- 節約の基本は「設定温度」と「こまめな電源オフ」
- 厚手のこたつ布団で熱を逃がさない
- 断熱シートで床からの冷気を防ぐ
- こたつの設置場所を工夫する
- 古いこたつは省エネモデルへの買い替えも検討
それぞれの節約術を詳しく解説します。
節約の基本は「設定温度」と「こまめな電源オフ」
最も簡単で効果的な節約術は、設定温度を適切に管理することです。
前述の通り、設定を「強」から「弱」に変えるだけで、電気代は半分近くになる可能性があります。
はじめは「強」で暖め、こたつの中が十分に暖まったら「弱」に切り替える習慣をつけるだけで、無駄な電力消費を抑えられます。
また、つけっぱなしとこまめに消すのどちらがよいかについては、離れる時間で判断するのがおすすめです。
こたつは起動時に多くの電力を消費するわけではないため、30分以上その場を離れる場合は、電源をオフにする方が節約につながると考えてよいでしょう。
最近では、人の動きを検知して自動で電源をオン、オフしてくれる人感センサー付きのモデルもあり、消し忘れ防止に役立ちます。
厚手のこたつ布団で熱を逃がさない
こたつで作り出した熱を、いかに外に逃がさないかという点も重要なポイントです。
こたつ布団は、熱を閉じ込めるための最も大切なアイテムといえるでしょう。
布団を選ぶ際は、保温性の高いマイクロファイバー素材などを選ぶのがおすすめです。
また、サイズも重要で、テーブルの天板サイズよりも1mほど大きいものを選ぶと、隙間ができにくく熱が逃げるのを効果的に防げます。
さらに、こたつ布団の上に「上掛け」と呼ばれるカバーを一枚追加するだけでも、保温性は大きく向上します。
断熱シートで床からの冷気を防ぐ
とくにフローリングの床にこたつを置く場合、床からの冷気で熱が奪われやすくなります。
これを防ぐのに効果的なのが、敷布団の下に敷く市販の「断熱シート」です。
アルミ素材などでできた断熱シートを一枚挟むだけで、床からの冷気をシャットアウトし、こたつの熱が床に逃げるのを防いでくれます。
保温効果が高まることで、低い設定温度でも十分な暖かさを維持でき、結果として電気代の節約につながるでしょう。
断熱シートは数百円〜数千円程度で購入できるものが多く、電気代の節約分を考えれば、十分に元が取れる投資といえます。
こたつの設置場所を工夫する
意外と見落としがちなのが、こたつを置く場所で、部屋のどこに置くかによっても、保温効率は変わります。
たとえば、窓際にこたつを置くと、窓から伝わる冷気によってこたつの熱が奪われやすくなり、効率が悪くなってしまいます。
できるだけ窓際を避け、部屋の中央や壁際に設置する方が、効率的に暖かさを保てるでしょう。
少し配置を変えるだけでも、無駄な電力消費を抑えられます。
古いこたつは省エネモデルへの買い替えも検討
もし10年以上同じこたつを使い続けている場合は、本体の買い替えを検討するのも一つの有効な手段です。
家電製品の省エネ技術は年々進化しており、最新のこたつはヒーターの効率が格段に向上しています。
たとえば、10年前の代表的な石英管ヒーター(消費電力600W)と最新のフラットカーボンヒーター(消費電力300W)を比較すると、1時間あたりの電気代が最大で約9.3円も変わる可能性があります。
また、前述の人感センサーなど、無駄な電力消費を防ぐ便利な機能が搭載されたモデルも増えています。
本体の購入費用はかかりますが、毎月の電気代の差額を考えれば、長期的な視点では買い替えた方がお得になる可能性も十分にあります。
【根本的な見直し】こたつの使い方だけでは電気代節約に限界がある可能性

ここまで、こたつの使い方を工夫する節約術を紹介してきましたが、「いろいろと試しているのに、なぜか電気代が安くならない」と感じている方もいるのではないでしょうか。
実はその原因は、個人の努力だけではコントロールしきれない、電気料金の仕組みそのものにあるかもしれません。
本章では、節約術だけでは対応が難しい電気代高騰の背景と、その根本的な解決策について解説します。
電気料金の仕組みと対策
- 近年の電気料金が値上がりしている背景
- 節約術を実践しても請求額が下がりにくい理由
- 電気代を根本から見直すなら「電力会社の切り替え」が最も効果的
なぜ電気代が下がりにくいのか、その理由から解説します。
近年の電気料金が値上がりしている背景
私たちが毎月支払っている電気料金は、いくつかの項目で構成されています。
具体的には、契約アンペアで決まる「基本料金」、使った分だけかかる「電力量料金」に加え、「燃料費調整額」や「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」などが含まれています。
この中でとくに注意が必要なのが、燃料費調整額です。
これは、発電に必要な化石燃料の価格変動を電気料金に反映させるもので、燃料価格が高騰すると、私たちの意思とは関係なく電気代が上がってしまう仕組みです。
近年の電気料金の値上がりは、この燃料費調整額の上昇が大きな要因の一つと考えられます。
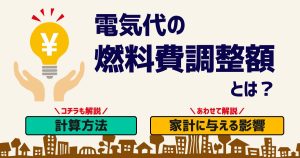
節約術を実践しても請求額が下がりにくい理由
こたつの設定温度を下げたり、こまめに電源を消したりして電気の使用量(kWh)を減らしても、請求額が思うように下がらないケースもあるでしょう。
その主な原因は、先ほど説明した燃料費調整額などの影響で、電気1kWhあたりの料金単価自体が上がっているためです。
たとえるなら、野菜の使用量を減らして食費を節約しようとしても、野菜そのものの値段が上がってしまえば、全体の食費はなかなか下がらないのと同じ状況です。
このように、個人の節電努力だけでは、電気代高騰の大きな波を乗り切るのが難しくなっているのが現状といえるでしょう。
電気代を根本から見直すなら「電力会社の切り替え」が最も効果的
個人の節電努力には限界があります。そこで電気代を根本から見直す有効な選択肢となるのが、契約している電力会社そのものを見直すことです。
2016年の電力自由化により、私たちは自身のライフスタイルに合った電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。
現在、多くの新電力会社が、地域の大手電力会社よりも割安な料金プランを提供しています。
電気料金の「単価」そのものが安い電力会社に切り替えることは、毎月の電気代を根本的に、そして継続的に引き下げるための最も効果的な手段の一つです。
賢く電力会社を選ぶことで、同じ量の電気を使用しても、毎月の支払額を大きく抑えることが可能になります。
【年間数千円お得に】電気代を確実に安くするなら「お得電力」がおすすめ
数ある新電力の中でも、「手続きが複雑そう」「どの会社を選べばよいかわからない」と感じる方におすすめなのが、シンプルな料金体系が魅力の「お得電力」です。
今お使いの電力会社から切り替えるだけで、こたつだけでなく、家庭全体の電気代を確実にお得にできる可能性があります。
ここでは、「お得電力」の具体的な魅力と、どれくらい電気代が安くなるのかについて解説します。
お得電力の魅力
- 「お得電力」とは?大手電力会社より常に安いシンプルな料金体系が魅力
- 【エリア・世帯別】お得電力に切り替えた場合の電気代削減額シミュレーション
- 申し込みは簡単3ステップ!切り替え方法と注意点
サービスの詳細を解説します。
「お得電力」とは?大手電力会社より常に安いシンプルな料金体系が魅力
「お得電力」の最大の特徴は、そのシンプルでわかりやすい料金体系にあります。
各エリアの大手電力会社が提供している標準的なプラン(従量電灯プラン)と比較して、基本料金と電力量料金がそれぞれ約3%安く設定されています。
複雑な割引条件やポイント制度はなく、電気を使う時間帯や使用量にかかわらず、切り替えるだけで誰もが電気代の削減メリットを享受できるのが魅力です。
運営している株式会社Qvouは、2025年時点で創業40年の歴史を持つ総合企業であり、人気商品「のむシリカ」の販売元でもあります。
長年の実績に裏打ちされた、安心して契約できる新電力サービスといえるでしょう。
【エリア・世帯別】お得電力に切り替えた場合の電気代削減額の目安
実際に「お得電力」に切り替えると、年間でどれくらいの電気代が節約できるのか、、エリア別、世帯人数別の年間削減額の目安を次の表にまとめました。
お得電力 年間削減額の目安
| エリア | 世帯人数 | 年間削減額(約) |
|---|---|---|
| 北海道 | 1人 | 3,202円 |
| 2〜3人 | 5,713円 | |
| 4〜6人 | 9,973円 | |
| 東北 | 1人 | 2,727円 |
| 2〜3人 | 4,894円 | |
| 4〜6人 | 8,657円 | |
| 東京 | 1人 | 2,665円 |
| 2〜3人 | 4,811円 | |
| 4〜6人 | 8,553円 | |
| 中部 | 1人 | 2,008円 |
| 2〜3人 | 3,563円 | |
| 4〜6人 | 6,259円 | |
| 北陸 | 1人 | 2,664円 |
| 2〜3人 | 4,675円 | |
| 4〜6人 | 8,054円 | |
| 関西 | 1人 | 1,641円 |
| 2〜3人 | 3,081円 | |
| 4〜6人 | 5,661円 | |
| 中国 | 1人 | 2,641円 |
| 2〜3人 | 4,807円 | |
| 4〜6人 | 8,557円 | |
| 四国 | 1人 | 2,519円 |
| 2〜3人 | 4,595円 | |
| 4〜6人 | 8,255円 | |
| 九州 | 1人 | 1,825円 |
| 2〜3人 | 3,289円 | |
| 4〜6人 | 5,832円 | |
| 沖縄 | 1人 | 3,144円 |
| 2〜3人 | 5,646円 | |
| 4〜6人 | 9,936円 |
たとえば、東京電力エリアにお住まいの4人家族の場合、年間で約8,553円もの電気代が安くなる計算です。
こたつを我慢したり、暖房の設定温度を下げたりしなくても、電力会社を切り替えるだけでこれだけの節約が見込めるのは、大きなメリットといえるでしょう。
申し込みは簡単3ステップ!切り替え方法と注意点
「お得電力」への申し込みは、非常に簡単です。
現在契約中の電力会社の「検針票」を元に、Webサイトから数分で手続きが完了します。
申し込みに必要なのは、検針票に記載されている「お客様番号」や「供給地点特定番号」などの情報です。
新電力への切り替えに際して、特別な工事や費用は一切かかりません。
また、電線などの設備はこれまで通り地域の電力会社のものを使用するため、電気の質が落ちたり、停電しやすくなったりする心配もありません。
安心して切り替えを検討してみてください。
なお、注意点として、解約時には事務手数料3,300円(税込)が発生します。
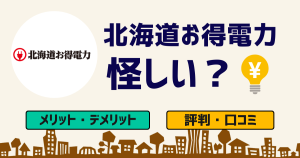
こたつの電気代に関するよくある質問

最後に、こたつの電気代に関してだけでなく、安全性や健康面でよく寄せられる質問について回答します。
安心してこたつを活用するために、ぜひ参考にしてください。
こたつに関するQ&A
- こたつで火事になる危険性はありますか?
- 毎日こたつで寝ても健康に問題はありませんか?
- ヒーターの種類で電気代は変わりますか?
それぞれの質問に詳しく回答します。
こたつで火事になる危険性はありますか?
はい、誤った使い方をすると火事になる危険性があります。
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)などの公的機関も注意を呼びかけていますが、主な原因としては、こたつ布団がヒーター部分に長時間触れることや、電源コードの劣化、損傷が挙げられます。
安全に使うための注意点
- 洗濯物などをこたつの中で乾かさない
- 電源コードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたりしない
- シーズンの使いはじめには、ヒーター部分のほこりを掃除し、電源コードに傷がないか確認する
- 就寝時や外出時など、長時間使用しない場合は電源プラグを抜いておく
これらの点に注意して、安全にこたつを使用しましょう。
出典:NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)「こたつの事故の防止について(注意喚起)」
毎日こたつで寝ても健康に問題はありませんか?
気持ちがよいため、こたつで寝てしまうという方もいるかもしれませんが、健康上のリスクがあるため推奨はできません。
主なリスクとして、「低温やけど」と「脱水症状」が挙げられます。
低温やけどは、体温より少し高い温度のものに長時間触れ続けることにより起きるやけどです。
痛みを感じにくいため、気づいたときには重症化しているケースもあります。
また、睡眠中は多くの汗をかきますが、こたつの中は高温で乾燥しやすいため、知らず知らずのうちに脱水症状に陥る危険性もあります。
こたつは就寝するための暖房器具ではないことを理解し、寝る際は必ず電源を切りましょう。
ヒーターの種類で電気代は変わりますか?
はい、ヒーターの種類によって消費電力や暖まり方が異なるため、電気代も変動します。
現在、家庭用こたつで主流となっているヒーターには、主に次のような種類があります。
主なヒーターの種類と特徴
- 石英管ヒーター:昔ながらのタイプで価格が安い。遠赤外線でじんわり暖まる。
- ハロゲンヒーター:電源を入れるとすぐに暖まる。石英管より寿命が長い。
- カーボンヒーター:ハロゲンよりさらに速暖性に優れ、遠赤外線放射量が多い。
- フラットカーボンヒーター:ヒーター部が薄型で、こたつの中が広く使える。省エネ性が高い。
一般的に、新しい技術が使われているヒーターほど省エネ性能が高い傾向にあります。
もし古いこたつの電気代が気になる場合は、ヒーターユニットだけを最新のものに交換する選択肢も検討してみるとよいでしょう。
まとめ

本記事では、こたつの電気代について、具体的な金額の目安からほかの暖房器具との比較、効果的な節約術、そして電気料金の根本的な見直し方までを解説しました。
こたつは経済的な暖房器具ですが、使い方を工夫し、さらに電気料金プランそのものを見直すことで、光熱費全体を大きく削減できる可能性があります。
冬の電気代でお悩みの方は、当記事で解説した数値を参考に、自身の状況に最適な判断をしてください。
とくに、電力会社の切り替えによる節約効果は大きいため、より詳細な情報は公式サイトで確認するか、サービス名「お得電力」で検索してみることをおすすめします。
<参考>
お得電力