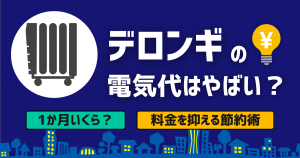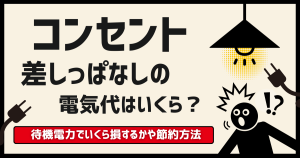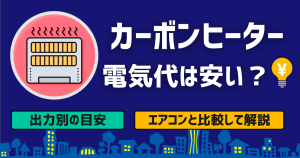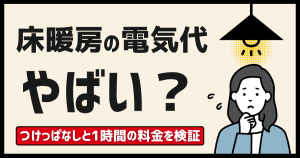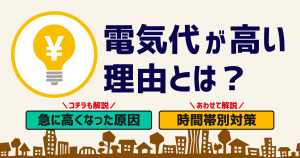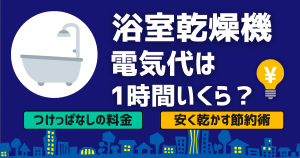パソコンのスリープ機能は、作業を一時的に中断してもすぐに再開できるため、非常に便利です。
しかし、「スリープ中の電気代はいくらかかるのか」「シャットダウンと比べて本当にお得なのか」などの疑問を持つ方も多いでしょう。
結論から述べると、PCの電源管理は90分を目安に使い分けることが節約の基本です。
本記事では、スリープとシャットダウンの電気代を比較し、ゲーミングPCやノートPCなど種類別の消費電力も、電力のプロの視点から解説します。
自身の使い方に最適な節約術がわかるため、電気代を少しでも抑えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
【結論】PCの電気代節約は「90分ルール」が基本

パソコンの電源をこまめに切るべきか、それともスリープ状態で待機させるべきか、電気代の観点から悩んでいる方もいるでしょう。
一般的なデスクトップPCを8時間つけっぱなし(起動状態)にした場合の電気代は、約10円〜20円にもなり、毎日続けると月々数百円の無駄なコストにつながる可能性があります。
実は、この問題には「90分」という一つの目安が存在します。
ここでは、PCの電気代を節約するための基本的な考え方について解説します。
- スリープとシャットダウンの電気代比較
- なぜ90分が使い分けの目安になるのか
- PCの状態別(起動・スリープ・シャットダウン)の消費電力の違い
ここからは、それぞれの項目について詳しく解説します。
スリープとシャットダウンの電気代を比較
結論から述べると、90分以内の離席であればスリープの方が、それ以上であればシャットダウンの方が電気代の節約につながる可能性があります。
なぜなら、PCが起動する際に多くの電力を消費するためです。
スリープとシャットダウン(待機電力)の電気代比較(目安)
| PCの種類 | 状態 | 1時間 | 8時間 | 24時間 |
|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC | スリープ(1W) | 約0.03円 | 約0.25円 | 約0.74円 |
| シャットダウン(0.5W) | 約0.02円 | 約0.12円 | 約0.37円 | |
| ノートPC | スリープ(0.5W) | 約0.02円 | 約0.12円 | 約0.37円 |
| シャットダウン(0.3W) | 約0.01円 | 約0.07円 | 約0.22円 |
※電力量料金単価は、全国家庭電気製品公正取引協議会の目安単価である31円/kWh(税込)で計算しています。
実際にマイクロソフト社の調査でも、PCを利用しない時間が90分以内であれば、シャットダウンするよりもスリープ状態にしておく方が消費電力を抑えられるという結果が示されています。
「90分ルール」を意識することが、賢い電気代節約の第一歩といえるでしょう。
なぜ90分が使い分けの目安になるのか
90分がスリープとシャットダウンの使い分けの目安とされる理由は、PCが起動時に大きな電力を消費するからです。
短時間の離席のたびにシャットダウンを繰り返すと、スリープ状態を維持するよりも多くの電力を消費してしまう可能性があります。
PCの電源を入れると、OSの起動や各パーツのチェックなどで一時的に消費電力が急上昇します。
そのため、1日に何度も電源のオンオフを繰り返す使い方は、かえって電気代を高くしてしまいかねません。
90分という時間は、起動時の消費電力とスリープ中の消費電力のバランスを考慮した、一つの合理的な目安といえるでしょう。
PCの状態別(起動・スリープ・シャットダウン)の消費電力の違い
PCの状態によって、消費される電力は大きく異なります。これは、状態ごとに電力を消費するパーツが違うためです。
起動中は、計算処理をおこなうCPUやメモリ、画面を表示するディスプレイ、グラフィックボードなど、大半のパーツがフル稼働するため、最も多くの電力を消費します。
一方、スリープ状態とは、作業内容をメモリに一時保存し、CPUなどの主要なパーツへの電力供給をほぼ停止させた状態のことです。
そのため、消費電力は一般的に1W程度まで大幅に抑えられます。
シャットダウン後は、基本的に電力は消費しませんが、コンセントに接続している限り、ごくわずかな待機電力を消費する点に注意しましょう。
【種類別】ゲーミングPCとノートPCのスリープ時の電気代を調査

一口にパソコンといっても、その種類によって消費電力は大きく異なります。
とくに、高性能なゲーミングPCは電気代が高いというイメージがあるかもしれません。
ここでは、PCの種類によるスリープ時の電気代の違いや、自身のPCの電気代を計算する方法について解説します。
- 一般的なデスクトップPC・ノートPCの電気代
- 【独自調査】人気ゲーミングPCの電気代は本当に高いのか
- スリープ時の電気代を自身で計算する方法
それぞれの内容を具体的に解説します。
一般的なデスクトップPC・ノートPCの電気代
一般的に、ノートPCはデスクトップPCに比べて消費電力が低い傾向にあります。
これは、ノートPCがバッテリーで駆動することを前提に、各パーツが省電力設計になっているためです。
たとえば、NECの公式サイトによると、一般的なビジネス向けノートパソコンの標準的な消費電力は約6.5W、スリープ時は約0.4Wと記載されています。
対して、一体型デスクトップパソコンでは標準時が約34W、スリープ時が約4.8Wとなっており、大きな差があることがわかります。
もちろん、製品のスペックや年式によって消費電力は変動しますが、省電力性能を重視する場合は、ノートPCを選ぶとよいでしょう。
スリープ時の電気代を自身で計算する方法
自身のPCの電気代を正確に知りたい場合は、次の計算式で算出できます。
消費電力(W) ÷ 1,000 × 時間(h) × 電力量料金単価(円/kWh)
まず、使用しているPCの消費電力を確認しましょう。消費電力は、製品の仕様書やメーカーの公式サイトで確認できます。
次に、電力量料金単価は、契約している電力会社の検針票や会員サイトで確認できます。
たとえば、スリープ時の消費電力が3WのPCを8時間スリープさせた場合、電力量料金単価が31円/kWhだとすると、「3W ÷ 1,000 × 8h × 31円/kWh = 約0.74円」です。
このように、自身の環境にあわせて電気代を計算してみてください。
の電気代は高い?1時間・1か月の料金目安と今日からできる節約術-300x158.jpg)
【実践編】シーン別!スリープ活用術と電気代以外のメリット・デメリット

電気代を節約するためには、PCの利用シーンに応じてスリープとシャットダウンを賢く使い分けることが重要です。
また、どちらを選択するのかにより、電気代のみならずPCの寿命や作業の快適性にも影響を与えます。
ここでは、具体的な活用術と、電気代以外のメリット・デメリットを解説します。
- スリープがおすすめのケース
- シャットダウンがおすすめのケース
- 電気代だけじゃない、PCの寿命や快適性への影響
自身の使い方と照らし合わせながら、最適な方法を見つけてみてください。
こんなときはスリープがおすすめ
90分以内の短時間の離席の際は、シャットダウンよりもスリープがおすすめです。
たとえば、お昼休憩や短時間の打ち合わせ、家事の合間など、すぐに作業に戻る可能性がある場合に適しています。
スリープの最大のメリットは、数秒で作業中の状態に復帰できることです。
シャットダウンのようにOSやアプリケーションをはじめから起動する必要がないため、時間を節約し、作業効率を大幅に向上させられます。
開いていたファイルやブラウザのタブもそのまま保持されるため、中断したところからスムーズに作業を再開できる点が魅力です。
こんなときはシャットダウンがおすすめ
長時間PCを使用しない場合は、シャットダウンを選ぶとよいでしょう。
具体的には、1日の作業がすべて終了した就寝時や、休日で丸一日PCに触れないときなどが挙げられます。
シャットダウンすることで、スリープ中に消費されるわずかな電力も完全にカットできるため、最も確実な節電方法です。
また、PCの電源を完全に切ることで、メモリがリフレッシュされて溜まった不要なデータがクリアされるため、PCの動作が安定するというメリットもあります。
さらに、落雷によるサージ電流からPCを守るという観点からも、長時間の不在時にはシャットダウンし、コンセントを抜いておくとより安心です。
電気代だけじゃない!PCの寿命や快適性への影響
スリープとシャットダウンの選択は、PCのパーツ寿命やパフォーマンスにもかかわってきます。
どちらか一方が絶対的によいというわけではなく、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
たとえば、シャットダウンを頻繁に繰り返すと、電源を入れるたびにハードディスク(HDD)やSSDなどの起動用ストレージに負荷がかかり、寿命を縮める可能性があります。
一方、スリープを長期間継続すると、メモリにデータが蓄積され続け、システムの動作が不安定になることも考えられます。
電気代の節約のみならず、PCを快適に長く使用するためには、短時間の離席はスリープ、長時間の不在はシャットダウンというように、バランス良く使い分けることが重要です。
PCの電気代をもっと根本から節約する方法も!

PCの電源管理を工夫することは大切ですが、削減できる電気代には限界があります。
より大きな節約効果を目指すなら、PC本体の設定や周辺機器、さらには電気の契約そのものを見直すことが有効です。
ここでは、PCの電気代を根本から節約するための3つの方法を紹介します。
- PC本体でできる消費電力の節約術
- 意外と見落としがちな周辺機器の待機電力
- 最も効果的な方法は電力会社のプランを見直すこと
今日からはじめられるものばかりであるため、ぜひ参考にしてみてください。
PC本体でできる消費電力の節約術
PCの設定を見直すのみでも、消費電力を手軽に抑えることが可能です。
まず試したい方法が、OSに標準で搭載されている省電力モードの活用です。
一定時間操作がない場合に自動でスリープに移行するよう設定することで、無駄な電力消費を防ぎます。
また、ディスプレイの輝度を下げることも非常に効果的です。
とくにノートパソコンの場合、画面の明るさを下げるのみで消費電力を大幅に削減できます。
その他、使用していないアプリケーションをこまめに終了させたり、ゲーミングPCの場合は不要なLEDライティングをオフにしたりすることも、地道な節約につながるでしょう。
意外と見落としがちな周辺機器の待機電力
PCの電気代を考える際、PC本体のみならず、接続されている周辺機器にも注意が必要です。
たとえば、モニターやプリンター、スピーカー、Wi-Fiルーターなどの周辺機器は、使用していない時間も待機電力を消費しています。
経済産業省 資源エネルギー庁の調査によると、一世帯あたりの年間消費電力量のうち、待機時消費電力量が占める割合は決して小さくありません。
上記の待機電力をまとめてカットするためには、節電タップの活用がおすすめです。
就寝前や外出時にスイッチを一つ切るのみで、すべての周辺機器の電源をオフにでき、手軽で効果的な節約術といえます。
最も効果的な方法は電力会社のプランを見直すこと
PC本体や周辺機器の節電対策は重要ですが、最も効果的な節約方法は、契約している電力会社の料金プランそのものを見直すことです。
家庭で消費する電力のうち、PCが占める割合は一部に過ぎません。
そのため、電気料金の単価自体を安くできれば、PCのみならず家全体の電気代を根本から削減できます。
2016年の電力自由化以降、ライフスタイルにあわせてさまざまな電力会社を自由に選べるようになりました。
現在の電気代が高いと感じる方は、よりお得な料金プランを提供している新電力への切り替えを検討してみるのもよいでしょう。
総務省統計局の家計調査でも、電気代は家計の中で大きな支出項目となっており、プランの見直しは家計改善に直結する可能性があります。
次の章で、シンプルでわかりやすく電気代を安くできる「お得電力」について詳しく解説します。
PCの電気代が気になるなら「お得電力」がおすすめです
「電力会社を見直すといっても、どこを選べばいいかわからない」と感じる方もいるでしょう。
現在大手電力会社と契約しており、シンプルに電気代を安くしたいと考えているなら、「お得電力」がおすすめです。
ここでは、「お得電力」が選ばれる3つの理由を解説します。
- 大手電力会社より安くなるシンプルな料金プラン
- 切り替え手続きは簡単、電気の品質もそのまま
- ライフスタイル別の電気代シミュレーション
なぜ「お得電力」が節約につながるのか、具体的に解説します。
大手電力会社より安くなるシンプルな料金プラン
「お得電力」の最大の魅力は、料金プランのわかりやすさにあります。
各地域の大手電力会社(東京電力や関西電力など)が提供している一般的な料金プランと比較して、基本料金と電力量料金の両方が安くなるように設定されています。
新電力の中には、特定のサービスとのセット利用や、複雑な条件を満たさないと安くならないプランも存在します。
しかし、「お得電力」は、現在契約している電力会社から切り替えるのみで、毎月の電気代がお得になるシンプルな料金体系です。
難しいことを考えずに電気代を節約したい方に、とくにおすすめの電力会社といえるでしょう。
切り替え手続きは簡単、電気の品質もそのまま
「電力会社の切り替えは手続きが面倒そう」と心配する方は多いものですが、お得電力への切り替えは非常に簡単です。
申し込みはWebサイトから最短5分で完了するうえ、切り替えに伴う工事や費用、自宅への訪問も原則として必要ありません。
また、現在契約中の電力会社への解約連絡も不要で、手間なくスムーズに切り替えが可能です。
さらに重要な点として、切り替え後も電気はこれまでと同じ大手電力会社の送配電網を使用して届けられます。
そのため、電気の品質が落ちたり、停電しやすくなったりする心配は一切ありません。
経済産業省も、電力会社を切り替えても供給の信頼性は変わらないと説明しており、安心して利用できます。
ライフスタイル別の電気代節約額目安
「お得電力」に切り替えることで、実際にどれくらい電気代が安くなるのでしょうか。
ここでは、具体的なライフスタイルを想定した節約額の目安を紹介します。
「お得電力」切り替えによる年間節約額の目安
| ライフスタイル | 想定 | 大手電力会社の場合(年間) | お得電力の場合(年間) | 年間節約額 |
|---|---|---|---|---|
| 一人暮らし (ゲーマー) | 30A / 300kWh/月 | 約134,000円 | 約130,000円 | 約4,000円 |
| 二人暮らし (テレワーク) | 40A / 400kWh/月 | 約178,000円 | 約172,000円 | 約6,000円 |
このように、とくに電気使用量が多い家庭ほど、切り替えによるメリットは大きくなる傾向があります。
PCでの作業やゲームで電気を多く使用する方にとって、「お得電力」は家計の強い味方になるでしょう。
【ライフスタイル別】サービス比較
| ライフスタイル |
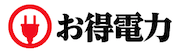
|

|
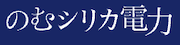
|
|---|---|---|---|
|
ケース1 共働きで 日中不在がち |
\おすすめ度/ 生活を変えず、確実に節約したい家庭に最適。シンプルに料金が安くなるのが最大のメリットです。 |
\おすすめ度/ 日中不在時は恩恵が少なめ。電気をよく使う朝晩・休日の価格高騰リスクに注意が必要です。 |
\おすすめ度/ 大手より安い料金+「のむシリカ」特典が魅力。標準的な使用量でもお得感をプラスできます。 |
|
ケース2 在宅ワーク中心で 昼間によく使う |
\おすすめ度/ 確実に安くなる安心感が魅力。大きな節約より、安定した割引を求める方におすすめです。 |
\おすすめ度/ 市場価格が安い昼間に電気を使えるため、電気代を大幅に削減できる可能性が最も高いプランです。 |
\おすすめ度/ 電気使用量が多い家庭に最適。「のむシリカ」特典を多く受け取れるため、料金+特典でお得です。 |
|
ケース3 家族が多く 電気使用量が多い |
\おすすめ度/ 使用量が多いほど削減額もアップ。シンプルに電気代を安くしたい家庭に最適です。 |
\おすすめ度/ 使用量が多いため、市場価格高騰時のリスクが大。時間帯を気にせず使う家庭には不向きです。 |
\おすすめ度/ 電気料金に応じて「のむシリカ」特典。電気使用量が最も多い家庭で、特典価値が最大になります。 |
PCの電気代に関するQ&A

ここでは、PCの電気代や電源管理に関して、多くの方が抱く疑問に回答します。
- ノートPCは電源に繋ぎっぱなしでも大丈夫?
- スリープからの復帰が遅いのですが、なぜですか?
- 休止状態との違いは何ですか?
ノートPCは電源につなぎっぱなしでも大丈夫?
最近のノートPCの多くは、バッテリーが満充電になると自動的に給電を停止する過充電防止機能が搭載されています。
そのため、電源アダプターにつなぎっぱなしにしても、すぐにバッテリーが故障するわけではありません。
ただし、常に100%の満充電状態で高温にさらされることは、バッテリーの劣化を早める一因とされています。
PCメーカーの多くは、バッテリーの寿命を長持ちさせるために、月に一度は電源アダプターを外し、バッテリー駆動でPCを使用することを推奨しています。
基本的には繋ぎっぱなしでも問題ありませんが、ときどきはバッテリーを動かしてみましょう。
スリープからの復帰が遅いのですが、なぜですか?
スリープからの復帰が遅くなる主な原因は、メモリ不足や常駐しているアプリケーションの多さ、ストレージの老朽化などが考えられます。
スリープは作業内容をメモリに保存するため、多くのアプリケーションを起動したままスリープさせると、復帰時にそれらを読み込むのに時間がかかることがあります。
対処法として、定期的にPCを再起動してメモリを解放することが効果的です。
また、PC起動時に自動で立ち上がる不要なスタートアップアプリを無効にすることも、動作の改善につながります。
それでも改善しない場合は、ストレージが原因の可能性もあるため、専門家への相談を検討しましょう。
休止状態との違いは何ですか?
休止状態とは、スリープと似ていますが、作業内容の保存先が異なります。
スリープが作業内容を電力消費の大きい「メモリ」に保存するのに対し、休止状態は電力消費のない「ストレージ(HDDやSSD)」に保存します。
そのため、休止状態はスリープよりも復帰に少し時間がかかりますが、電力を全く消費しないというメリットがあります。
ノートPCでバッテリー残量が少なくなった際に、作業内容を保持したまま電源を切りたい場合に有効です。
短時間の離席はスリープ、長時間使用しない場合はシャットダウン、その中間的な使い方として休止状態があると考えるとよいでしょう。
まとめ

本記事では、PCのスリープ機能にかかる電気代と、シャットダウンとの上手な使い分けについて解説しました。
90分以内の離席はスリープ、それ以上はシャットダウンが節約の基本ですが、ゲーミングPCやノートPCなど種類によって消費電力は異なります。
PCの電源管理も重要ですが、電気代を根本から見直すなら電力会社の切り替えが最も効果的です。
ぜひ当サイトの情報を参考に、家庭に最適なプランを検討してみてください。
より手軽でお得なプランの詳細は、「お得電力」の公式サイトでも確認してみてください。
<参考>
お得電力