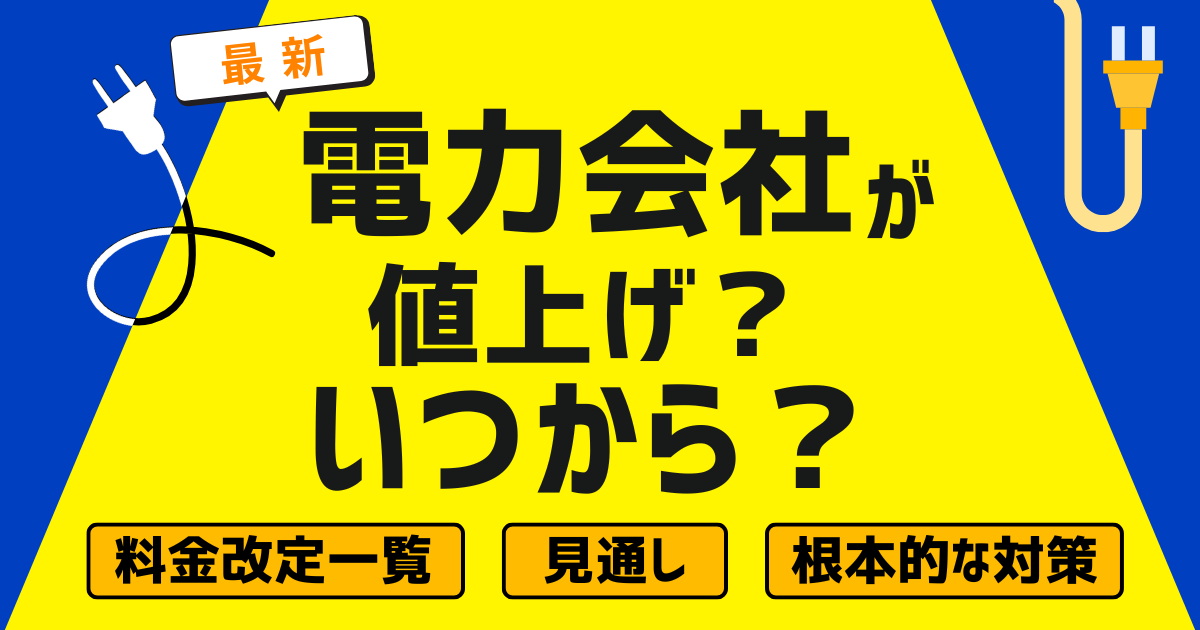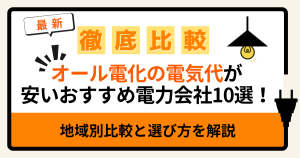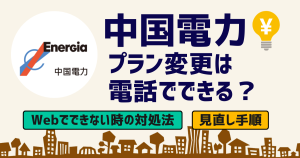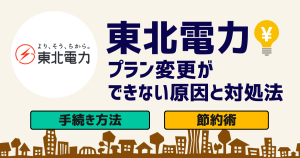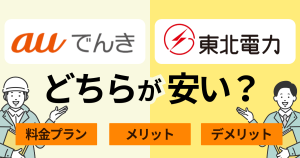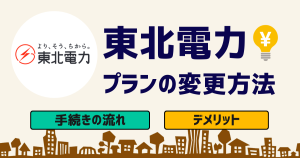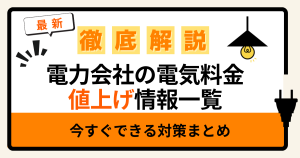近年の電気料金の値上げは、多くの方にとって家計の大きな悩みとなっています。
「なぜこんなに高くなるのか」「大手電力会社と新電力で違いはあるのか」といった疑問を感じる方も少なくありません。
結論として、電気料金の値上げは複数の要因が絡む構造的な問題であり、今後も上昇傾向が続く可能性があります。
本記事では、電力会社が値上げをおこなう根本的な理由から、政府の補助金政策の最新動向、そして私たちが今すぐ取り組める具体的な対策までをわかりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、自身の状況に合った最適な選択肢を見つけたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
【2026年最新】電力会社の電気料金はいつから値上げ?今後の見通しを解説

日本の電力会社の電気料金は、複数の要因が絡み合い、全体として値上げの傾向が続いています。
今後の見通しを立てるうえで、とくに重要となるポイントは次の3つです。
- 2026年1月からの政府補助金再開と今後の動向
- 大手電力会社の料金改定・値上げ状況一覧
- 長期的な電気料金は今後も上昇傾向が続く可能性
ここからは、各項目について詳しく解説します。
2026年1月からの政府補助金再開と今後の動向
政府による電気料金の負担軽減策である「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が、2026年1月使用分から3月使用分までの3か月間、一時的に再開される予定です。
しかし、2026年4月以降の支援については未定となっており、補助金が再度終了した場合は、その分だけ家計の負担が実質的に増加する可能性があります。
そのため、この補助金はあくまで一時的な措置と理解しておくことが重要です。
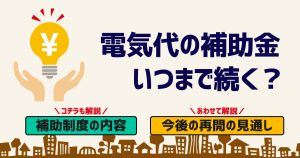
大手電力会社の料金改定・値上げ状況一覧
現在、東京電力や関西電力といった全国の大手電力会社においても、料金の見直しや値上げの動きが進んでいます。
とくに、電気料金に含まれる燃料費調整額の算定に見直しが入り、これまで設けられていた上限が撤廃されるケースも出てきました。
これにより、燃料価格が高騰した際に、その影響が直接電気料金に反映されやすくなります。
| 電力会社 | 燃料費調整額の上限 | 直近の動向・備考 |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 撤廃済み※ | 2025年10月から値上げ |
| 東北電力 | 撤廃済み※ | 2025年11月から値上げ |
| 東京電力 | 撤廃済み※ | 2025年4月に一部プランで値上げ |
| 中部電力 | 撤廃済み※ | 2024年4月に一部プランで値上げ |
| 北陸電力 | 撤廃済み※ | 動向を注視する必要あり |
| 関西電力 | 撤廃済み※ | 動向を注視する必要あり |
| 中国電力 | 撤廃済み※ | 動向を注視する必要あり |
| 四国電力 | 撤廃済み※ | 動向を注視する必要あり |
| 九州電力 | 撤廃済み※ | 2025年4月に一部の自由料金プランで値上げ |
| 沖縄電力 | 撤廃済み※ | 動向を注視する必要あり |
各社の詳しい料金改定状況については、契約している電力会社の公式サイトで最新の情報を確認しましょう。
長期的な電気料金は今後も上昇傾向が続く可能性
政府による一時的な補助金が再開されたものの、2026年4月以降の支援については未定であり、補助金の終了後は家計の負担が実質的に増加する可能性があります。
後ほど詳しく解説する電気料金の根本的な値上げ要因は、依然として解決されていません。
そのため、長期的な視点で見れば、電気料金への上昇圧力は今後も継続する可能性が高いと考えられます。
このような状況において、日々の生活や家計を守るためには、場当たり的な対応ではなく、根本的な電気料金対策を検討することが、これまで以上に重要になるといえるでしょう。
なぜ?電力会社の電気料金が値上げされる3つの根本的な理由

最近の電気料金の値上げは、特定の電力会社のみの問題ではなく、日本の電力業界全体が直面している構造的な課題に起因します。
主な理由として、次の3つが挙げられます。
- 理由1:世界情勢に連動する燃料費の高騰
- 理由2:毎年見直される再エネ賦課金の負担増
- 理由3:電気代を緩和していた政府の補助金終了・縮小
それぞれの理由を具体的に解説します。
理由1:世界情勢に連動する燃料費の高騰
電気料金が値上げされる最も大きな原因の一つが、発電に使われる燃料の価格高騰です。
日本の電力は、その多くを液化天然ガス(LNG)や石炭を燃料とする火力発電に頼っていますが、これらの燃料の大半を海外からの輸入に依存しています。
そのため、国際情勢の不安定化や円安の進行は、燃料の調達コストを直接押し上げる要因となります。
この燃料費の変動分は、「燃料費調整額」という項目で毎月の電気料金に反映される仕組みになっており、世界情勢の動きが私たちの電気代に直結しているのです。
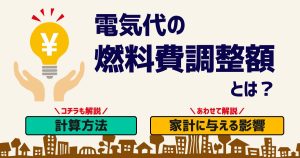
理由2:毎年見直される再エネ賦課金の負担増
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」、通称「再エネ賦課金」の単価が年々上昇していることも、値上げの要因となっています。
再エネ賦課金とは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを普及させる目的で、電気を使用するすべての方が負担するお金のことです。
この単価は毎年見直されており、2025年度には1kWhあたり3.98円へと引き上げられました。
今後も再生可能エネルギーの導入が進むにつれて、この賦課金がさらに上昇する可能性は高く、電気料金を押し上げる一因として考えられます。
出典:再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します (METI/経済産業省)
理由3:電気代を緩和していた政府の補助金終了・縮小
政府による電気料金の補助制度が終了、または縮小されたことも、多くの家庭で「値上げ」として実感される大きな理由です。
この補助金は、近年の急激なエネルギー価格の上昇から家計を守るための、あくまで一時的な負担緩和策でした。
2026年1月からの再開も期間限定の措置であり、この制度による値引きがなくなると、本来の電気料金が請求されるため、実質的な負担が増加することになります。
したがって、補助金の有無に左右されない、根本的な電気料金の見直しが重要になるといえるでしょう。
電気代の値上げは家計にいくら影響?世帯人数別の平均から対策を考えよう

電気料金の値上げが続くと、実際に家計にどの程度の影響が出るのか、不安に思う方も多いでしょう。
ここでは、公的な統計データから家庭の電気代の平均を確認し、値上げによる影響と、それに対して個人で取り組める対策について解説します。
【政府統計】世帯人数別の平均電気代はいくら?
まず、自身の電気代が平均と比べてどのくらいなのかを把握してみましょう。
総務省統計局がおこなっている家計調査によると、世帯人数別の電気代平均月額は次のとおりです。
| 世帯人数 | 電気代平均月額(2024年度) |
|---|---|
| 1人暮らし | 6,756円 |
| 2人世帯 | 10,878円 |
| 3人世帯 | 12,651円 |
| 4人世帯 | 12,805円 |
| 5人世帯 | 14,413円 |
| 6人世帯 | 16,995円 |
出典:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯
季節やライフスタイルによって電気使用量は大きく変動しますが、これらの数値を一つの目安として、自宅の電気料金と比較してみてください。
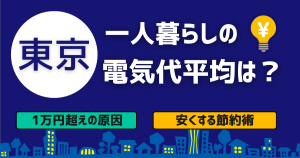
値上げが家計に与える負担額のシミュレーション
電気料金の値上げは、具体的に家計へどのくらいの負担増となるのでしょうか。
たとえば、前述した再エネ賦課金の単価上昇のみでも、月に400kWhの電気を使用する標準的な家庭(二人以上世帯)の場合、年間で約2,352円、月々約196円の負担増となります。
つまり、二人以上世帯の平均的な電気代である月額約12,008円が、この要因のみでも約12,204円に上昇する見込みです。
加えて、政府の補助金が2026年4月以降なくなることを考慮すると、さらに負担が増える可能性があります。
このように、一つ一つの値上げは小さな額に見えても、年間を通すと家計に大きな影響を与えることがわかります。
自分でできる対策は「節電」と「電力会社の見直し」
こうした状況に対し、個人が主体的に取り組める対策は、大きく分けて2つあります。
一つは、日々の生活の中で電気の無駄遣いをなくす「節電」です。
エアコンの温度を適切に設定したり、古い家電を省エネ性能の高い製品に買い替えたりすることが挙げられます。
そしてもう一つが、契約している電力会社や料金プランそのものを見直す「電力会社の切り替え」です。
これら二つの対策を組み合わせることで、値上げ時代においても賢く電気代を抑えることが可能になります。
【値上げ対策の結論】電気代を安くするなら電力会社の見直しが最も効果的

電気代を節約するためには、日々の節電と電力会社の見直しの両方が重要です。
しかし、根本的な解決を目指すのであれば、契約先の電力会社を見直すことが最も効果的な対策といえるでしょう。
その理由と、失敗しない電力会社の選び方について解説します。
節電の努力だけでは値上げ分のカバーに限界がある理由
日々の節電は非常に大切ですが、電気料金の単価自体が上昇している現在、使用量を減らす努力のみでは値上げ分をカバーしきれないケースが増えています。
とくに、記録的な猛暑や厳しい冬には、健康を維持するためにある程度の冷暖房の使用は避けられません。
無理な節電は、生活の質を下げてしまう可能性もあります。
そのため、根本的な料金単価がより安い電力会社へ契約を切り替えることが、無理なく節約を続けるための有効な手段となるのです。
電力自由化で消費者が得られる選択のメリット
2016年4月からはじまった「電力自由化」により、私たちは自身のライフスタイルや価値観に合った電力会社を自由に選べるようになりました。
新電力へ切り替えた場合でも、電気はこれまでと同じ大手電力会社の送配電網から届けられるため、電気の品質が落ちたり、停電が増えたりする心配は一切ありません。
数多くの電力会社の中から、よりお得な料金プランを提供している会社を自身で選べることが、電力自由化の最大のメリットといえるでしょう。
失敗しない電力会社の選び方3つのポイント
数ある電力会社の中から、自身に合った会社を選ぶためには、いくつかのポイントがあります。
選び方のポイント
- 料金プランがシンプルでわかりやすいか
- 自身のライフスタイルに合っているか
- 運営会社に信頼性や安定性があるか
とくに電気料金の値上げが続く現在は、複雑な条件がなく、今の契約よりもシンプルに安くなる料金プランを提供している電力会社を選ぶことが、失敗しないための重要なポイントです。
電気代の値上げが不安な方にはシンプルに安くなる「お得電力」がおすすめ
ここまで解説してきた選び方のポイントを踏まえると、電気代の値上げが不安な方にとくにおすすめしたいのが、新電力サービス「お得電力」です。
お得電力は、わかりやすい料金体系と、運営会社の信頼性が魅力です。
- お得電力とは?大手電力会社より確実に安くなる料金体系の仕組み
- 【世帯別】お得電力への乗り換えで期待できる年間節約額
- 申し込みは簡単3ステップ!切り替え手続きの流れと必要なもの
- 運営会社は創業40年以上で安心!株式会社Qvouの信頼性
それぞれの魅力について、具体的に紹介します。
お得電力とは?大手電力会社より確実に安くなる料金体系の仕組み
お得電力の最大の魅力は、そのシンプルでわかりやすい料金体系にあります。
このサービスは、各地域の大手電力会社が提供する主要な料金プランを基準とし、それよりも確実に安くなるように料金が設定されています。
毎月の固定費である「基本料金」と、使った分だけかかる「電力量料金」の両方が安くなるため、電気の使用量にかかわらず、多くの方が切り替えによるメリットを実感しやすい仕組みです。
【世帯別】お得電力への乗り換えで期待できる年間節約額
お得電力に乗り換えることで、実際にどのくらいの電気代を節約できるのでしょうか。
公式サイトの目安によると、たとえば東京電力エリア(従量電灯B)の場合、次のような節約額が期待できます。
お得電力への乗り換えによる年間節約額の目安
| 世帯人数 | 試算条件 | 年間節約額(約) | 5年間節約額(約) |
|---|---|---|---|
| 1人世帯 | 30A、200kWh | 2,665円 | 13,324円 |
| 2〜3人世帯 | 40A、350kWh | 4,811円 | 24,055円 |
| 4〜6人世帯 | 50A、600kWh | 8,553円 | 42,766円 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。
このように、自身の世帯に置き換えて具体的なメリットをイメージしやすい点も、お得電力の魅力といえるでしょう。
申し込みは簡単3ステップ!切り替え手続きの流れと必要なもの
お得電力への申し込みは、非常に簡単な3ステップで完了します。
申し込みの流れ
- Webの申し込みフォームに必要事項を入力
- 手続き完了のメールを確認
- 次回の検針日から利用開始
申し込みは最短5分で完了し、切り替えに伴う工事や、現在契約している電力会社への解約連絡も原則不要です。
手元に電気の「検針票」を用意すると、記載されている供給地点特定番号などを入力するのみで、スムーズに手続きを進められます。
なお、お得電力の解約時には、事務手数料として3,300円(税込)がかかるため、事前に確認しておくと安心です。
運営会社は創業40年以上で安心!株式会社Qvouの信頼性
お得電力を運営しているのは、株式会社Qvouという企業です。
株式会社Qvouは、2025年時点で創業40年の歴史を持つ総合企業であり、電力事業以外にも多角的な事業を展開しています。
とくに、太陽光発電事業においては1,400件を超える豊富な施工実績があり、エネルギー分野に関する深い知見と安定した経営基盤を持っています。
新電力の契約に際して運営会社の安定性を重視する方にとっても、安心して選べるサービスといえるでしょう。
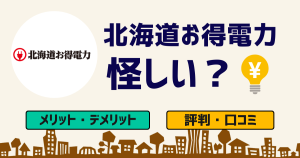
電力会社の値上げに関するQ&A

最後に、電力会社の値上げに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。
電気代が急に倍になった原因は?
電気代が急に倍になったと感じる場合、本記事で解説した「燃料費の高騰」や「政府補助金の終了」といった外部要因が大きく影響している可能性が高いでしょう。
それに加えて、猛暑によるエアコンの長時間利用など、家庭での電気使用量が前年同月と比べて大幅に増えているケースも考えられます。
まずは電気の検針票を確認し、「電気ご使用量(kWh)」が昨年と比べてどう変わっているかをチェックすることをおすすめします。
新電力は倒産が不安だけど大丈夫?
過去に一部の新電力会社が事業から撤退した事例があるのは事実です。
そのため、電力会社を選ぶ際には、運営会社の経営基盤が安定しているかを確認することが一つの重要なポイントになります。
万が一、契約中の新電力会社が倒産した場合でも、電気が突然止まることはありません。
地域の電力会社が電気を供給する「最終保障供給」というセーフティーネットがあるため、過度に心配する必要はないでしょう。
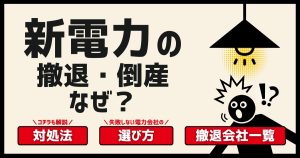
オール電化プランも値上げされる?
オール電化プランも値上げの対象です。
オール電化向けの料金プランも、燃料費調整額や再エネ賦課金の影響を受けるため、これらの単価が上昇すれば、結果として電気料金は値上がりします。
お得電力では、大手電力会社のオール電化向けプランと同等のプランも用意しています。
現在オール電化プランを契約中の方も、ぜひ一度見直しを検討してみてください。
まとめ

本記事では、電力会社が電気料金を値上げする根本的な3つの理由と、今後の見通し、そして家計への影響を軽減するための具体的な対策について解説しました。
電気料金の値上げは、燃料費の高騰や国の制度変更といった外部要因が大きく、個人の努力のみでは吸収しきれない状況になっています。
このような時代だからこそ、最も効果的な対策は、自身のライフスタイルに合った、より安価な料金プランを提供する電力会社へ見直すことです。
電気料金の見直しについては、当サイトの情報を参考に、自身にとって最適な判断をしてください。
シンプルでわかりやすく、確実に安くなる料金プランを探している方は、サービス名「お得電力」で検索し、公式サイトで詳細を確認してみてください。
<参考>
お得電力