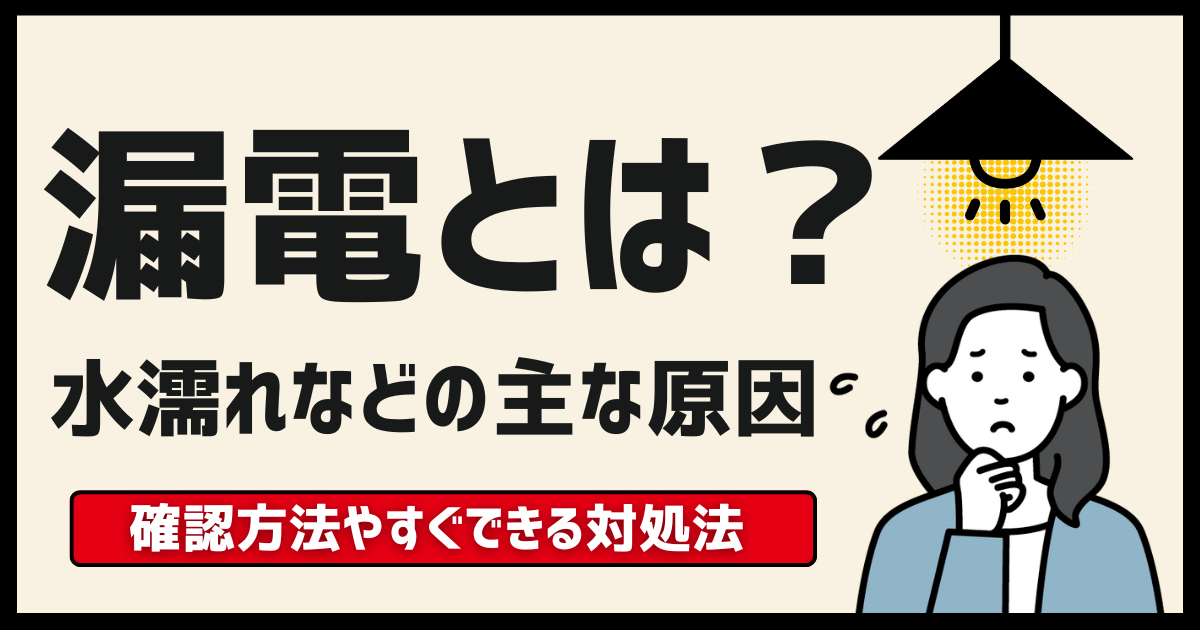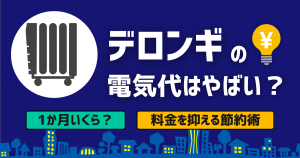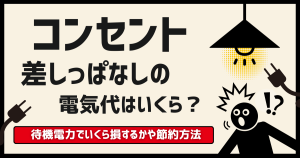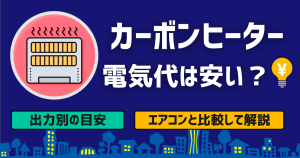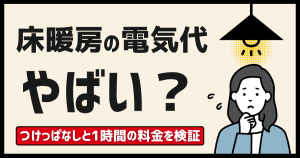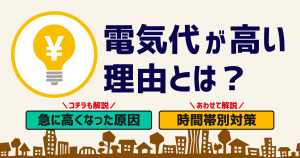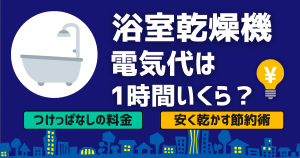私たちの生活に電気は欠かせないものです。
しかし、ブレーカーが頻繁に落ちる、電気代が急に高くなったなどの異常があると、「もしかして漏電では」という大きな不安を感じる方も少なくありません。
結論として、漏電は放置すると感電や火災につながるため非常に危険ですが、その原因と対処法を知ることで被害を防ぐことが可能です。
本記事では、漏電の基本的な仕組みや水濡れなどの主な原因、自身でできる確認方法から修理費用の相場までを網羅的に解説します。
漏電への不安を解消したい方、万が一の事態に備えたい方は、ぜひ参考にしてください。
漏電とは電気が本来のルートから漏れ出す危険な現象

ブレーカーが頻繁に落ちる、家電に触れるとピリッとする、といった経験はありませんか。
それは「漏電」のサインかもしれません。
この章では、漏電がどのような現象で、なぜ危険なのかについて、次の3つのポイントから解説します。
- 漏電の仕組みと危険性
- 漏電を放置した場合に起こりうること
- ショートとの違い
それぞれの内容を具体的に見ていきましょう。
漏電の仕組みと感電や火災につなぐ理由
漏電とは、電気が本来通るべき回路、つまり電線の中などから外へ漏れ出してしまう現象のことです。
通常、電気はゴムやビニールといった電気を通しにくい「絶縁体」で覆われた電線の中を流れています。
しかし、この絶縁体が劣化したり傷ついたりすると、そこから電気が漏れ出し、家電の金属部分や建物の構造体に流れることがあります。
この漏れ出た電気に人が触れると、人の体が電気の通り道となることで「感電」という非常に危険な事故につながる可能性があるため注意が必要です。
また、漏電している箇所では熱や火花が発生しやすく、近くにホコリや可燃物があると、それが原因で「火災」が発生するおそれもあります。
実際に、消防庁のデータでも電気設備が原因となる火災は毎年発生しており、漏電はその主要な原因の一つと考えられています。
出典:東京消防庁│漏電による火災の事例と火災予防対策について
放置は絶対に危険!漏電が引き起こす最悪の事態
漏電のサインに気づきながら「まだ大丈夫だろう」と放置するのは危険です。
漏電を放置すると、人命に関わる感電事故や、大切な家や財産をすべて失いかねない大規模な火災につながるリスクがあります。
また、危険性のみでなく経済的な損失も無視できません。
漏電している状態は、電気が常にどこかへ流れ出ている状態のため、使っていないはずの電力が消費され続け、電気代が不自然に高騰する原因となります。
このように、漏電の放置は安全面でも経済面でも、深刻な事態を引き起こす可能性があるため、早期の発見と対処が何よりも重要です。
【補足】漏電とショートの違い
漏電とよく似た電気トラブルに「ショート」があります。
どちらもブレーカーが作動する原因となるため混同されがちですが、現象としては全く異なるものです。
| 漏電 | ショート | |
|---|---|---|
| 現象 | 電気が本来の経路から外へ漏れ出る状態 | 本来つながらない電線同士などが直接接触する状態 |
| 危険性 | 感電や火災のリスク(じわじわとした危険) | 火花や発熱、発火のリスク(衝撃的な危険) |
| 発生例 | コードの破損部に水がかかり、床に電気が流れる | コンセント内部で、電気が流れる部分同士が金属片などで接触する |
漏電が「電気が回路から漏れ出す」現象であるのに対し、ショートは電気回路のプラスとマイナスが何らかの原因で直接接触し、そこに一気に大きな電流が流れる現象を指します。
どちらも危険な状態であることに変わりはありませんが、その仕組みには明確な違いがあるのです。
この違いを理解しておくことは、電気トラブルの原因を考えるうえで役立つでしょう。
漏電の主な原因は水濡れや経年劣化、ホコリの蓄積
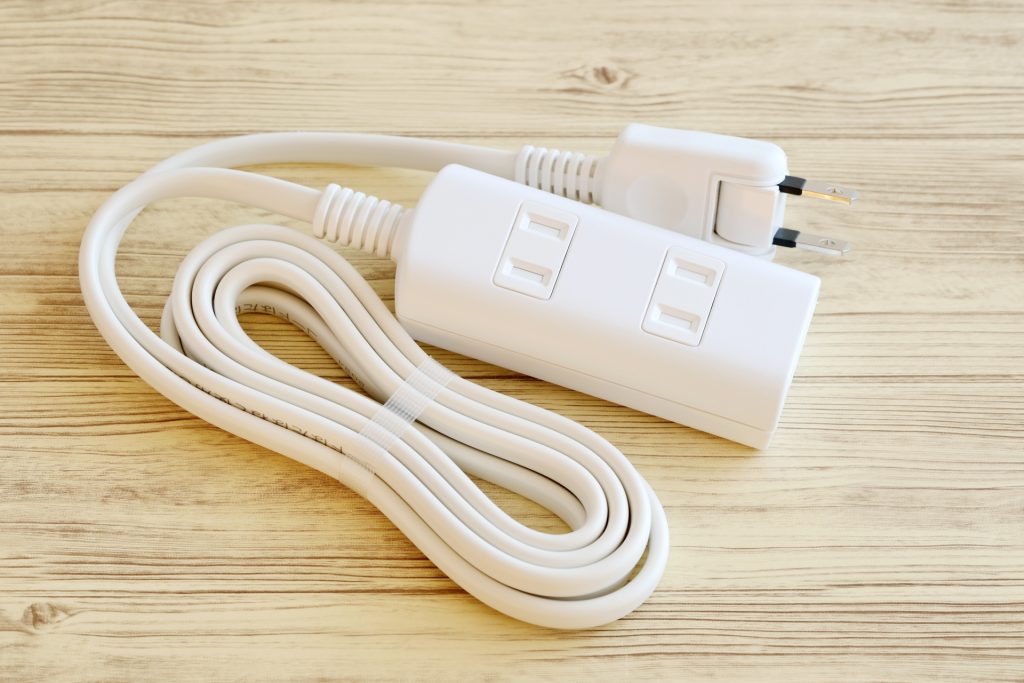
漏電は特別なことではなく、私たちの身の回りのささいなことがきっかけで発生する可能性があります。
ここでは、漏電を引き起こす主な原因として、代表的な3つのケースを紹介します。
- コンセントやコード周りの水濡れ
- 絶縁体の経年劣化やコードの損傷
- ホコリと湿気が原因のトラッキング現象
これらの原因を知り、日々の生活で注意することが漏電の予防につながります。
最も多い原因はコンセントやコード周りの水濡れ
漏電の最も一般的で多い原因は「水濡れ」です。
水は電気を通しやすい性質を持っているため、コンセントや電源コード、家電製品そのものに水がかかると、そこから電気が漏れ出すことがあります。
とくに、キッチンや洗面所、トイレといった水回りは注意が必要です。
また、屋外に設置されたコンセントや、台風などの際に雨水が吹き込んで濡れてしまうケースも考えられます。
過去には、雨漏りが原因で天井裏の配線から漏電し、火災に至ったという事例もあります。
水気のある場所で電気製品を使用する際は、水が飛び散らないように注意することが大切です。
絶縁体の経年劣化やコードの損傷も大きな原因
家電製品を長年使用していると、電気コードにも見えないところで劣化が進んでいます。
電線を覆っているゴムやビニールの「絶縁体」は、長期間の使用による熱や、設置場所によっては紫外線などの影響で、硬くなったりひび割れたりすることがあります。
この絶縁体が劣化、もしくは破損すると、中の電線が露出して漏電の原因となるのです。
また、経年劣化のみでなく、物理的な損傷にも注意が必要です。
家具の下敷きになってコードが圧迫されたり、ドアに挟まれたり、コードを強く折り曲げたりすることも、絶縁体の損傷につながります。
普段見えない場所にある配線も、定期的に点検することが望ましいでしょう。
ホコリと湿気が引き起こすトラッキング現象
コンセントと電源プラグの隙間に溜まったホコリが原因で発生する「トラッキング現象」も、漏電火災の危険な原因の一つです。
トラッキング現象とは、コンセントに差し込んだプラグの周辺に溜まったホコリが、空気中の湿気を吸うことで電気を通しやすい状態になり、プラグの刃の間で火花放電が繰り返される現象を指します。
この放電によってプラグが徐々に炭化し、最終的に発火に至るのです。
冷蔵庫やテレビの裏など、壁際に設置されていて普段あまり掃除をしない場所のコンセントは、とくに注意が必要です。
火災を防ぐためにも、コンセント周りは定期的に乾いた布で清掃し、ホコリが溜まらないように心がけましょう。
漏電のサインは分電盤の漏電ブレーカーで確認できる

漏電は目に見えないため、発生に気づきにくいことがあります。
しかし、家庭内で起こるいくつかのサインから、漏電の可能性を察知することが可能です。
ここでは、自身でできる漏電のチェック方法として、次の3つのポイントを解説します。
- 分電盤の漏電ブレーカーの確認
- 電気代の不自然な高騰
- 家電に触れた際の異常や異臭
これらのサインを見逃さず、早期発見につなげましょう。
まずは分電盤の漏電ブレーカーを確認
家庭で漏電が発生しているかどうかを最も簡単に確認できる方法は、分電盤の「漏電ブレーカー」をチェックすることです。
分電盤は、玄関や洗面所などに設置されている箱で、中には複数のブレーカーが並んでいます。
この中で、多くの場合「テスト」と書かれた赤いボタンが付いているものが漏電ブレーカーです。
もし、この漏電ブレーカーのスイッチが落ちていれば、家のどこかで漏電が発生している可能性が非常に高いといえます。
また、漏電していなくても、漏電ブレーカーが正常に機能するかを確認することも重要です。
テストボタンを押してみて、ブレーカーのスイッチが正常に「切」に切り替われば、正しく作動している証拠です。
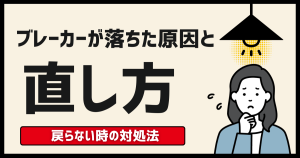
電気代の不自然な高騰は漏電の可能性
電気代の不自然な高騰は、漏電のサインである可能性があります。
漏れ出た電気も電力メーターで計測されるため、結果として電気の使用量が増え、電気代が高くなってしまうのです。
実際に、古いエアコンの室外機の配線が原因で漏電し、月の電気代が普段より5,000円も高くなったという事例もあります。
原因不明の電気代高騰は、放置せずに原因を調べることが大切です。
漏電による電気代への影響シミュレーション(目安)
| 漏電電流 | 1時間あたりの電力消費 | 1か月(30日)の電気代増加額(目安) |
|---|---|---|
| 30mA | 約3.3W | 約71円 |
| 100mA | 約11W | 約238円 |
| 300mA | 約33W | 約713円 |
※電圧110V、電力量料金単価27円/kWhで計算した場合の理論値です。実際の金額を保証するものではありません。
電気代の明細を毎月確認し、不自然な増加がないかをチェックする習慣をつけることも、漏電の早期発見につながるでしょう。
家電に触れると痺れる、焦げ臭いなどの症状
分電盤や電気代のみでなく、五感で感じる異常も漏電の重要なサインとなります。
とくに注意したいのが、家電製品に触れたときの感覚です。
冷蔵庫や洗濯機といった、金属部分が多い家電に触れた際に、ピリピリと静電気のような刺激を感じた場合は注意が必要です。
これは、家電の内部で発生した漏電が、筐体を伝わって体に流れようとしているサインかもしれません。
また、コンセントの差し込み口やその周辺が黒く変色している、プラスチックが溶けたような焦げ臭い匂いがするといった異常も、非常に危険な兆候です。
漏電を察知したら安全確保の上、専門業者に連絡する

もし自宅で漏電のサインを察知したら、どのように行動すればよいのでしょうか。
慌てて間違った対処をすると、感電などの二次被害につながるおそれがあります。
ここでは、漏電が疑われる場合に取るべき行動を、3つのステップに分けて解説します。
- ステップ1:安全のため家電のコンセントを抜く
- ステップ2:漏電ブレーカーで発生箇所を特定する
- ステップ3:専門業者に連絡する
正しい手順を知り、落ち着いて行動することが大切です。
ステップ1:安全のため家電のコンセントを抜く
漏電が疑われる際に最も優先すべきは、自身の安全確保です。
感電のリスクを避けるため、まずは漏電の原因と思われる家電製品の電源プラグをコンセントから抜きましょう。
このとき、必ず乾いた手で作業することが重要です。
手が濡れていると電気が伝わりやすくなり、感電の危険性が高まります。
また、ブレーカーが落ちているからと、原因がわからないままいきなりスイッチを「入」にするのも危険です。
まずは身の安全を確保し、落ち着いて次のステップに進みましょう。
ステップ2:漏電ブレーカーで発生箇所を特定する
漏電ブレーカーが落ちて家全体の電気が使えなくなった場合、簡単な操作で漏電している回路を特定できる可能性があります。
これにより、問題のない回路だけ電気を復旧させ、専門業者が到着するまでの間、最低限の電化製品を使用できるようになります。
漏電箇所の特定手順
- 分電盤のアンペアブレーカーと漏電ブレーカーを「切」にする
- すべての安全ブレーカー(小さいスイッチ)を「切」にする
- アンペアブレーカーと漏電ブレーカーを「入」にする
- 安全ブレーカーを一つずつ順番に「入」にしていく
- 特定の安全ブレーカーを「入」にした瞬間に漏電ブレーカーが落ちたら、その回路が漏電している箇所
この手順で漏電箇所を特定したら、その回路の安全ブレーカーのみを「切」にした状態で、再度漏電ブレーカーを「入」にすれば、ほかの部屋の電気は復旧します。
専門業者に連絡する際も、どの回路で問題が起きているかを伝えられると、その後の調査がスムーズに進むでしょう。
ステップ3:電力会社または電気工事店に連絡する
漏電の原因調査や修理は、専門的な知識と技術が必要であり、「電気工事士」の資格を持つ方でなければおこなえません。
漏電箇所が特定できた場合も、自身で修理しようとするのは危険なため避けてください。
まずは、契約している電力会社のカスタマーセンターや、住んでいる地域の電気工事店に連絡し、状況を説明して点検を依頼しましょう。
どこに連絡すればよいかわからない場合は、地域の電気保安協会に相談するのも一つの方法です。
もし賃貸物件に住んでいる場合は、自身で業者を手配する前に、必ず大家さんや管理会社に連絡して指示を仰いでください。
出典:電気保安協会全国連絡会
漏電を予防するために今日からできる4つの対策

普段の少しの心がけで、漏電のリスクは大幅に減らせます。
ここでは、今日から実践できる具体的な予防策を4つ紹介します。
アース線を正しく接続する
洗濯機や電子レンジなど、水回りで使用する家電は必ずアース線を接続しましょう。
アース線は、万が一漏電した際に電気を地面に逃がし、感電を防ぐ命綱です。
コンセント周りを定期的に清掃する
冷蔵庫やテレビの裏など、ホコリが溜まりやすい場所のコンセントは定期的に乾いた布で清掃し、トラッキング現象を防ぎましょう。
タコ足配線をやめる
一つのコンセントから多くの電力を使用しすぎると、コードが発熱し絶縁体の劣化を早める原因になります。
タコ足配線は避け、壁のコンセントを使いましょう。
コードの扱い方に注意する
電源コードを家具で踏みつけたり、ドアに挟んだり、きつく束ねたりしないように注意しましょう。
コードに負担がかかると、断線や絶縁体の破損につながります。
漏電の調査・修理にかかる費用相場
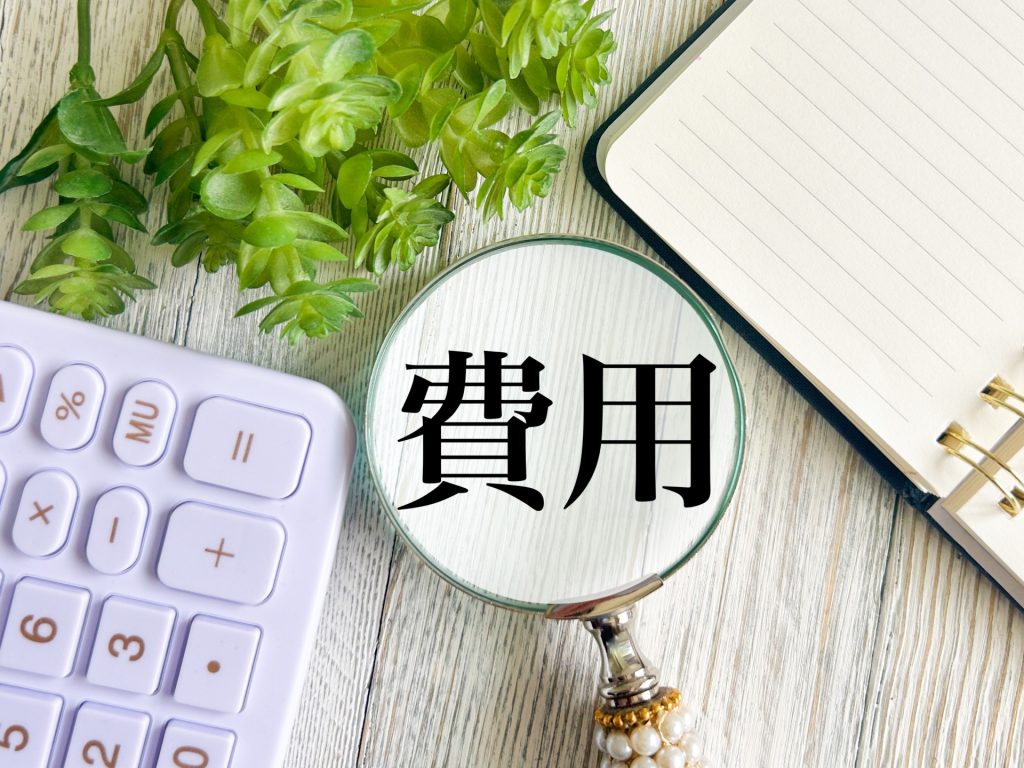
漏電の修理を専門業者に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのかは気になるところでしょう。
費用は漏電の原因や修理内容によって大きく異なりますが、事前に費用の内訳や相場を知っておくと安心です。
ここでは、漏電の調査・修理にかかる費用について、次の3つの観点から解説します。
- 費用の内訳
- 具体的な費用相場
- 火災保険が適用されるケース
万が一のときに慌てないためにも、費用の目安を把握しておきましょう。
費用の内訳は出張費・調査費・作業費
専門業者に漏電修理を依頼した場合の費用は、主に次の3つの項目で構成されるケースが一般的です。
費用の主な内訳
- 出張費:業者が現場まで駆けつけるための費用
- 調査費・点検費:漏電の原因を特定するための調査や点検にかかる費用
- 作業費・部品代:実際の修理や、劣化したコンセント・配線などの部品交換にかかる費用
業者によっては、見積もりが無料の場合や、出張費と調査費がセットになっている場合もあります。
正式に依頼する前には必ず見積もりを取り、費用の内訳が明確に記載されているかを確認することが大切です。
複数の業者から見積もりを取って比較検討するのもよいでしょう。
【費用相場】調査のみなら8,000円から、修理は内容により変動
漏電修理の具体的な費用は、状況によって大きく変動しますが、一般的な相場は存在します。
漏電の原因を特定するための調査のみで完了した場合の費用相場は、8,000円〜15,000円程度が目安です。
その後、修理が必要になった場合の費用は、作業内容によって加算されます。
たとえば、コンセント一箇所の交換であれば5,000円前後から、壁の中の配線を修理するような大掛かりな工事になると数万円以上かかることもあります。
あくまで一般的な相場であり、夜間や休日の対応では割増料金が発生する場合もあるため、依頼時に必ず確認するようにしましょう。
落雷などが原因の場合は火災保険が使える可能性も
漏電の修理費用は、場合によっては自身が加入している火災保険でカバーできる可能性があります。
とくに、漏電の原因が「落雷」によるものであった場合、多くの火災保険に付帯している「電気的・機械的事故特約」の補償対象となるケースがあります。
この特約は、漏電以外にも、ショートや過電流によって家電製品が故障した場合の修理費用なども補償してくれるものです。
ただし、保険が適用される条件は契約内容によって異なるため、すべてのケースで使用できるわけではありません。
もし落雷など自然災害が原因の場合は、依頼前に一度契約の保険会社に連絡し、補償の対象となるかを確認してみることをおすすめします。
漏電トラブルを機に毎月の電気代を見直してみよう

漏電の調査や修理には、予期せぬ出費が伴うことがあります。
このような突然の出費は、家計にとって少なからず負担となるでしょう。
しかし、このトラブルをきっかけに、毎月の生活に欠かせない「電気代」そのものを見直してみてみるのも一つの手です。
固定費である電気代を削減できれば、今回の修理費用を長期的にカバーすることも可能かもしれません。
漏電修理の思わぬ出費を固定費削減でカバー
漏電修理にかかる費用は、数千円から数万円と、決して安い金額ではありません。
このような一時的な大きな出費があると、家計のやりくりが大変になることもあるでしょう。
一方で、私たちが毎月必ず支払っている電気代のような「固定費」は、一度見直すのみで、その後の節約効果が長く続くという特徴があります。
たとえば、月々の電気代を2,000円削減できれば、年間で24,000円もの節約につながります。
これは、漏電の調査や修理費用を十分にカバーできる金額といえるでしょう。
総務省統計局の家計調査によると、二人以上世帯の月平均の電気代は約12,008円(2024年)となっており、電気代は家計の中でも大きな割合を占めています。
予期せぬトラブルを、家計全体を見直すよい機会と捉えることもできるのです。
電力会社の切り替えは簡単!電気の質は変わらない
電気代を見直すうえで、現在最も手軽で効果的な方法の一つが「電力会社の切り替え」です。
2016年の電力自由化により、私たちは自身のライフスタイルに合った電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。
「新電力に切り替えると、電気が不安定になったりしないか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、その心配は不要です。
どの電力会社と契約しても、実際に電気を家庭に届けるための送電網は、これまでと同じ地域の電力会社(一般送配電事業者)のものを利用します。
そのため、切り替えによって電気の品質が落ちたり、停電しやすくなったりすることはありません。
電力会社の切り替えは、電気の質を変えることなく、毎月の電気代を賢く節約できる有効な手段といえるでしょう。
電気代をシンプルに安くするならお得電力がおすすめ
数ある新電力の中から、どれを選べばよいか迷ってしまう方もいるでしょう。
もし、複雑な料金プランは苦手で、とにかくシンプルに電気代を安くしたいと考えているなら「お得電力」がおすすめです。
ここでは、「お得電力」の魅力について、次の3つのポイントから紹介します。
- シンプルで分かりやすい料金体系
- エリア別の電気代削減シミュレーション
- お得電力がおすすめな方の特徴
なぜ「お得電力」が選ばれるのか、その理由を解説します。
大手電力会社より常に約3%安いシンプルな料金体系
「お得電力」の最大の特徴は、そのシンプルでわかりやすい料金体系です。
各エリアの大手電力会社が提供する一般的なプラン(従量電灯プラン)と比較して、電気の基本料金と、使用した分のみかかる電力量料金が、どちらも常に約3%安く設定されています。
新電力の中には、時間帯によって料金が変わるプランや、複雑な割引条件があるプランも少なくありません。
しかし、「お得電力」なら、電気を使う時間帯や使用量を気にすることなく、誰でも確実に電気代の削減メリットを実感できます。
このサービスを運営する株式会社Qvouは、2025年時点で創業40年の歴史を持つ総合企業であり、安心して契約できる点も魅力です。
【エリア別】電気代は年間これだけ安くなる
「お得電力」に切り替えると、実際にどれくらい電気代が安くなるのでしょうか。
ここでは、エリアと世帯人数ごとに、年間の電気代削減額の目安を一覧で紹介します。
北海道エリア
| 世帯人数 | 試算条件 | 年間削減額 | 5年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 1人世帯 | 30A、200kWh | 3,202円 | 16,009円 |
| 2~3人世帯 | 40A、350kWh | 5,713円 | 28,564円 |
| 4~6人世帯 | 50A、600kWh | 9,973円 | 49,866円 |
東京エリア
| 世帯人数 | 試算条件 | 年間削減額 | 5年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 1人世帯 | 30A、200kWh | 2,665円 | 13,324円 |
| 2~3人世帯 | 40A、350kWh | 4,811円 | 24,055円 |
| 4~6人世帯 | 50A、600kWh | 8,553円 | 42,766円 |
関西エリア
| 世帯人数 | 試算条件 | 年間削減額 | 5年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 1人世帯 | 200kWh | 1,641円 | 8,204円 |
| 2~3人世帯 | 350kWh | 3,081円 | 15,404円 |
| 4~6人世帯 | 600kWh | 5,661円 | 28,304円 |
なお、試算額には消費税が含まれていますが、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まれていません。その他のエリアの削減額については、公式サイトで確認してください。
とにかく電気代を安くしたい・手続きが簡単な方がいい人におすすめ
ここまで紹介した特徴から、「お得電力」はとくに次のような方におすすめのサービスといえるでしょう。
お得電力がおすすめな方
- とにかくシンプルに電気代を安くしたい方
- 現在、大手電力会社を契約中の方
- 複雑な料金プランの計算や比較が面倒だと感じる方
- 簡単な手続きで電力会社を切り替えたい方
申し込みに必要なものは、現在契約中の電力会社の検針票(電気ご使用量のお知らせ)のみです。
手続きはWebサイトから簡単におこなえるため、漏電トラブルを機に家計の見直しを検討している方は、ぜひ「お得電力」を選択肢の一つとして考えてみてください。
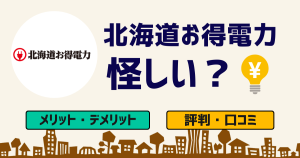
漏電に関するよくある質問

最後に、漏電に関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で回答します。
新電力に契約していても漏電対応はしてもらえますか
どの電力会社と契約していても、漏電時の対応は問題なく受けられます。
漏電の調査や、電柱から家庭までの送電設備に関するトラブル対応は、契約している小売電気事業者(新電力など)ではなく、その地域を管轄する「一般送配電事業者」の役割です。
一般送配電事業者とは、東京電力パワーグリッドや関西電力送配電といった、大手電力会社の送配電部門を指します。
そのため、契約先が新電力でも、従来と変わらない体制で迅速に対応してもらえます。
賃貸マンションやアパートで漏電した場合は誰が費用を負担しますか
賃貸物件で漏電した場合の費用負担者は、その漏電の原因によって異なります。
一般的に、壁の中の配線、備え付けのエアコンや給湯器といった建物の設備の老朽化が原因であれば、その修理費用は大家さんや管理会社の負担となります。
一方で、入居者自身が持ち込んだ家電製品の故障や、水をこぼしてしまったなどの不注意が原因である場合は、入居者の負担となるのが通例です。
判断に迷うケースも多いため、漏電が疑われる場合は、まず大家さんや管理会社に連絡して状況を報告し、指示を仰ぐようにしましょう。
アース線がない家電はどのように対策すればいいですか
アース線は、万が一製品が漏電した際に、漏れた電気を安全に地面へ逃がすことで感電を防ぐものです。
もしコンセントにアース線を接続する端子がない場合、最も安全で確実な対策は、電気工事店に依頼してアース端子付きコンセントを増設してもらうことです。
工事が難しい場合の次善策としては、コンセントに差し込むのみで漏電を検知して電気を遮断してくれる「漏電保護タップ」を使用する方法もあります。
自身の安全を守るためにも、適切な対策を講じることが大切です。
まとめ

本記事では、漏電の基本的な仕組みから、水濡れや経年劣化といった主な原因、そして漏電のサインを見つける方法や安全な対処法について解説しました。
漏電は火災や感電のリスクを伴う非常に危険な現象ですが、その兆候は分電盤の確認や日々の電気代チェックで早期に発見できます。
万が一、漏電が疑われる場合は、自身で解決しようとせず、安全を確保したうえで速やかに専門業者へ連絡することが何よりも重要です。
電気の安全に関するトラブルについては、電力の専門家である当サイトの情報を参考に、適切な判断をしてください。
また、漏電修理後の家計負担を軽減したいと考えている方は、公式サイトで「お得電力」の詳細を確認するか、サービス名で検索してみてください。
<参考>
お得電力