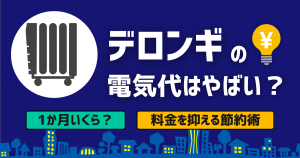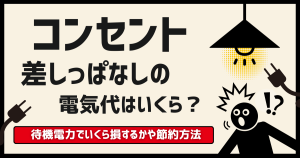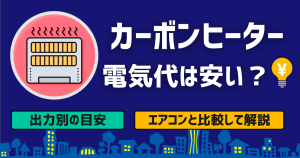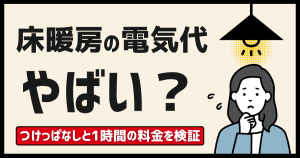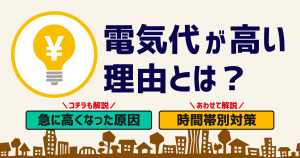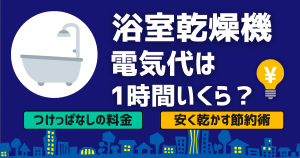賃貸物件などで手軽に設置できる窓用エアコンですが、「電気代が高い」という評判から購入や使用を躊躇している方も多いでしょう。
結論として、窓用エアコンの電気代は壁掛け式より高くなる傾向にありますが、使い方を工夫し、さらに電力プランを見直すことで費用を抑えることは可能です。
本記事では、1時間、つけっぱなしの場合の具体的な電気代シミュレーションから、今日から実践できる5つの節約術、そして最も効果的な電気料金プランの見直しまでを詳しく解説します。
電気代への漠然とした不安を解消し、自身の状況に合った最適な選択をおこないたい方は、ぜひ参考にしてください。
【結論】窓用エアコンの電気代は壁掛けより高い傾向にある | ただし節約は可能!

窓用エアコンを検討する際、多くの方が気になるのが電気代ではないでしょうか。
結論からいうと、窓用エアコンの電気代は壁掛けタイプより高くなる傾向があります。
しかし、使い方や選び方を工夫すれば、電気代を抑えることは十分に可能です。
ここでは、具体的な電気代の目安から、安く抑えるためのポイントまで詳しく解説します。
1時間・1か月・つけっぱなしの電気代シミュレーション
1時間あたりの電気代は「消費電力(W)÷ 1,000 × 使用時間(h)×電気料金単価(円/kWh)」という計算式で算出できます。
消費電力が600Wのモデルを想定した場合、1時間、1か月、つけっぱなしの電気代は次のとおりです。
| 使用状況 | 電気代 | 備考 |
|---|---|---|
| 1時間 | 18.6円 | |
| 1か月(30日) | 4,464円 | 1日8時間使用と仮定 |
| つけっぱなし | 13,392円 | 30月間24時間運転を仮定 |
消費電力が600Wのモデルの場合、電気料金単価を31円/kWhとすると、1時間あたりの電気代は約18.6円です。
上記の条件を基に1日8時間、月30日使用すると、1か月の電気代は約4,464円となります。
もし24時間つけっぱなしにした場合は、1か月で約1万3千円を超える計算になり、家計への影響も大きくなることがわかります。
自身の使い方に合わせて、まずは大まかな電気代の目安を把握することが重要です。
壁掛けエアコンとの電気代の具体的な比較
次の表は、窓用エアコンと壁掛けエアコンの電気代を比較したものです。
| 使用状況 | 窓用エアコン | 壁掛けエアコン |
|---|---|---|
| 想定消費電力 | 600W | 400W |
| 1時間 | 18.6円 | 12.4円 |
| 1か月 (30日1日8時間使用) | 4,464円 | 2,976円 |
| つけっぱなし (30月間24時間連続運転) | 13,392円 | 8,928円 |
電気代を比較すると、壁掛けエアコンの方が安くなる場合が一般的です。
壁掛けエアコンの多くが「インバーター制御」という、室温に応じて運転を細かく調整し、無駄な電力消費を抑える効率的な機能を搭載しているためです。
同じ畳数向けのモデルで比較した場合、年間で数千円から1万円以上の差額が出ることもあります。
ただし、窓用エアコンは本体価格が安く、設置工事も基本的に不要なため、初期費用を抑えられる点がメリットです。
そのため、短期的な利用か長期的な利用かによって、トータルコストを比較検討することが賢明といえるでしょう。
窓用エアコンの電気代が高くなる主な理由
窓用エアコンの電気代が高くなる主な理由は、その構造にあります。
熱を発生させるコンプレッサーと室内に冷風を送る部分が一体になっているため、壁掛けエアコンに比べて熱効率が下がりやすい傾向があります。
また、窓に取り付ける構造上、本体と窓枠の間にどうしても隙間が生まれやすく、そこから室内の冷たい空気が逃げたり、外の熱気が入ったりします。
これが冷房効率の低下につながり、結果として余分な電力消費が生まれ、電気代が高くなる原因となるのです。
シンプルな機能の製品が多い点も、省エネ性能で差が出る一因と考えられます。
電気代が安い窓用エアコンの選び方のポイント
電気代を意識して窓用エアコンを選ぶ際は、いくつかのポイントを確認することが重要です。
まず、省エネ性能の指標となる「期間消費電力量」をチェックしましょう。
期間消費電力量の数値が小さいほど、年間の電気代が安くなる目安となります。
また、部屋の広さである畳数に合った冷房能力のモデルを選ぶことも大切です。
必要以上に大きな能力の機種は無駄な電力を消費し、反対に小さすぎると部屋が冷えるまで時間がかかり、結果的に電気代が高くなる可能性があります。
最近では、人感センサーなどの便利な省エネ機能を搭載したメーカーの機種も登場しているため、ぜひ参考にしてみてください。
【実践編】今日からできる!窓用エアコンの電気代を安くする5つの節約術

窓用エアコンの電気代は、日々の使い方を少し工夫するのみで効果的に節約できます。
特別な道具がなくてもすぐに実践できるものばかりなため、ぜひ家庭で試してみてください。
ここでは、今日からはじめられる具体的な5つの節約術を詳しく解説します。
設定温度を適切に保ち自動運転を活用する
窓用エアコンの電気代を節約する基本は、設定温度の管理です。
冷房時の設定温度を27℃から28℃に上げるのみで、年間で約820円もの電気代節約効果が期待できるといわれています。
体への負担を考慮すると、外の気温との差が5〜6℃程度になるように設定するのがおすすめです。
また、風量の設定は「自動運転」を活用しましょう。自動運転は、室温を効率的に下げるために最適な風量へ自動で調整します。
手動で常に強風に設定しておくよりも無駄な電力消費を抑えられ、快適さと節電の両立が可能です。
サーキュレーターや扇風機を併用して空気を循環させる
サーキュレーターや扇風機との併用は、非常に効果的な節約方法です。
冷たい空気は部屋の下の方に溜まる性質があるため、サーキュレーターなどで空気をかき混ぜ、室温を均一にすることで、窓用エアコンの効率を大きく向上させられます。
体感温度も下がるため、エアコンの設定温度を普段より1〜2℃高くしても快適に過ごせるでしょう。
サーキュレーターや扇風機の電気代はエアコンに比べてごくわずかです。
手間を加えることで、無理なく快適に電気代を節約できるでしょう。
カーテンや断熱シートで窓からの熱の出入りを防ぐ
夏場に室温が上がる大きな原因は、窓から入り込む日差しです。
実は、室内に入ってくる熱の約7割が窓からといわれており、この熱を遮断することが冷房効率を高める鍵となります。
遮光・遮熱効果のあるカーテンを日中から閉めておくことで、直射日光を防ぎ、室温の上昇を抑えることが可能です。
さらに効果を高めたい場合は、窓に貼るタイプの断熱シートもおすすめです。
また、窓用エアコン設置時にできた窓枠との隙間を、市販の隙間テープで十分に塞ぐことも、冷気が逃げるのを防ぐ地道ながら重要な対策となります。
フィルターを定期的に掃除して運転効率を維持する
窓用エアコンのフィルター掃除は、手軽にできて効果の高い節約術です。
フィルターにホコリが溜まっていると、空気の通り道が塞がれることで、部屋を冷やすためにより多くのパワーが必要になります。
その結果、運転効率が低下し、無駄な電気代がかかります。
掃除の目安は、2週間に1回程度です。フィルターを取り外してホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いするだけで構いません。
簡単なメンテナンスを定期的におこなうのみで、冷房効率が維持され、年間で見ると数千円単位の電気代節約につながる場合もあります。
つけっぱなし運転が有効なケースと注意点
「エアコンはつけっぱなしの方が電気代が安い」と聞いたことがある方も多いでしょう。
これは、エアコンが最も電力を消費するのが、電源を入れてから設定温度になるまでの間だからです。
そのため、30分から1時間程度の短い時間の外出であれば、電源をオフにせず、つけっぱなしにしておいた方が、トータルの消費電力を抑えられる可能性があります。
ただし、部屋の断熱性や外気温、窓用エアコン自体の性能によって結果が大きく変わる点に注意が必要です。
長時間の外出時や、断熱性の低い部屋では、こまめに電源をオフにする方が節約につながるでしょう。
節約術だけでは限界?電気代を根本から見直す最も効果的な方法

日々の節約術も大切ですが、電気代の削減に限界を感じることもあるでしょう。
とくに在宅時間が長いと、エアコンの使用時間を減らすのも難しいかもしれません。
ここでは、電気代を根本から見直す最も効果的な方法について解説します。
電気代の料金内訳と家庭の節約努力の限界
毎月の電気代は、主に「基本料金」と、電気の使用量に応じて決まる「電力量料金」で構成されています。
本記事で紹介してきた節約術は、このうち「電力量」を減らすための努力です。
もちろん、無駄な電力消費を減らす努力は重要ですが、効果には限界があります。
とくに、リモートワークや猛暑などで在宅時間が長く、エアコンを長時間使わざるを得ない家庭では、これ以上使用量を減らすのは難しいと感じるのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、料金の仕組みそのものを見直すという考え方です。
なぜ電力会社の切り替えが根本的な解決策になるのか
2016年の電力自由化によって、私たちは自身のライフスタイルに合った電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。
電力会社を切り替えることの最大のメリットは、電気料金の単価そのものを安くできる可能性がある点です。
これまでの節約術が電気の「使用量」を減らすアプローチだったのに対し、電力会社の切り替えは電気の「単価」を下げるアプローチといえます。
電気代の単価を下げることで、窓用エアコンの使用を我慢するといった無理な節約をせずとも、電気代全体の削減が期待できるのです。
失敗しない電力会社選びで確認すべき3つのポイント
電力会社選びで確認すべきポイントは、主に次の3つです。
- 料金体系がシンプルでわかりやすいか
- 今までと同じ品質の電気が使用できるか
- 手続きが簡単で余計な費用や縛りがないか
まず、複雑な条件がなく、料金体系がシンプルでわかりやすいサービスを選びましょう。
次に、切り替えても電気の品質が変わらず、停電が増える心配がないかという点も安心のために不可欠です。
加えて申し込み手続きが簡単で、工事費などの初期費用や契約期間の縛り、解約金などの余計な負担がないかも事前に確認しておくとよいでしょう。
上記3つのポイントを満たす電力会社を選ぶことが、安心して電気代を節約するための秘訣となります。
窓用エアコンの電気代を賢く抑えるならお得電力がおすすめ
前述した電力会社選びのポイントを踏まえると、とくにおすすめしたいのが「お得電力」です。
なぜ「お得電力」が窓用エアコンの電気代に悩む方に適しているのか、3つの理由から具体的に紹介します。
理由1:今の使い方を変えずに大手電力会社より電気代が安くなる
「お得電力」の最大のメリットは、その圧倒的なわかりやすさです。
現在契約している大手電力会社の料金プランやサービス内容はそのままに、電気代の基本料金と電力量料金の両方が安くなる仕組みとなっています。
そのため、複雑なプランを比較検討したり、生活スタイルを変えたりする必要はありません。
「お得電力」に切り替えるというアクションのみで、今よりも電気代が安くなります。
たとえば、東京電力の従量電灯Bを利用の場合、電力使用量によっては年間で数千円から1万円以上の電気代が削減できる可能性があります。
理由2:供給される電気の品質は今まで通りで安心して使用できる
「電気料金が安くなるのは嬉しいけれど、停電が増えたりしないか心配」と感じる方もいるでしょう。
しかし電力会社を切り替えても、家庭に電気を届けるための送配電網は、これまで通り居住地域の大手電力会社のものを利用します。
そのため「お得電力」に切り替えた場合でも、電気の品質や安定供給、停電時の対応などは今までと全く変わりません。
運営会社である株式会社Qvouは、長年の事業実績を持つ信頼できる企業です。
安さのみでなく、インフラとしての変わらない安心感も「お得電力」が選ばれる理由の一つといえるでしょう。
理由3:申し込みは最短5分で完了し工事や費用も一切不要
電力会社の切り替えと聞くと、「手続きが面倒そう」というイメージを持つかもしれません。
しかし「お得電力」であれば、申し込みはスマートフォンやパソコンから、最短5分で完了します。
切り替えに伴う特別な工事や、現在契約中の電力会社への面倒な解約連絡も一切必要ありません。
もちろん、初期費用や手数料、契約期間の縛りや解約金もないため、リスクなく気軽に試すことが可能です。
ストレスフリーな手続きの簡便さが、多くの方にとって切り替えの心理的なハードルを大きく下げているといえます。
窓用エアコンと電気代に関するQ&A

ここでは、窓用エアコンの電気代や使い方に関して、多くの方が抱きやすい疑問に回答します。
より安心して窓用エアコンを利用するための参考にしてみてください。
暖房を使うと電気代はもっと高くなりますか?
一般的にエアコンは、冷房時よりも暖房時の方が消費電力が大きく、電気代が高くなる傾向にあります。
なぜなら、冬の方が夏よりも外気温と設定温度との差が大きくなり、部屋を暖めるためにより多くのエネルギーを必要とするからです。
とくに窓用エアコンは、製品によっては暖房機能がついていない、あるいは暖房効率があまり高くないモデルも存在します。
もし暖房での使用も考えている場合は、消費電力や対応畳数をよく確認することが重要です。
ほかの暖房器具、たとえばこたつなどと賢く併用することも節約につながるでしょう。
古い窓用エアコンでも節約や電力会社の切り替えは有効ですか?
古い窓用エアコンを使用している場合でも、節約術や電力会社の切り替えは有効です。
むしろ、古い機種は最新機種に比べて省エネ性能が低い傾向があるため、本記事で紹介したフィルター掃除やカーテンの活用といった節約術の効果はより重要になります。
また、電力会社の切り替えによる電気単価の引き下げは、機種の新旧にかかわらず効果を発揮します。
消費電力が大きい古い機種ほど、単価が下がることによる電気代の削減額が大きくなる可能性もあり、メリットを実感しやすいと考えられます。

窓用エアコンの設置や取り外しで他に注意すべきことはありますか?
窓用エアコンを設置する際は、まず自宅の窓が設置条件を満たしているかの確認が最も重要です。
窓の高さや開き方によっては、取り付けができない場合があります。
また、運転時の騒音や振動についても考慮が必要です。
とくに集合住宅に住んでいる場合は、隣室や階下への影響がないか事前に確認しておくと安心でしょう。
シーズンオフなどで長期間使用しない場合は、取り外して適切に保管することで、製品の劣化を防ぎ、寿命を延ばすことにつながります。
取り扱い説明書をよく読み、正しく設置・保管することが大切です。
ゴキブリなどの虫が隙間から入ってこないか心配です。
窓用エアコンの設置で、虫の侵入を心配される方は少なくありません。
構造上、どうしても窓と本体の間に隙間ができるため、侵入のリスクをゼロにすることは難しいのが現状です。
最も効果的な対策は、設置の際に、付属のパッキンや市販の隙間テープ、パテなどを使用して、考えられる隙間を十分に塞ぐことです。
また、エアコン内部で発生した水を排出するためのドレンホースの出口から虫が侵入するケースもあります。
この対策として、ホースの先端に防虫キャップを取り付けるのも有効な方法といえるでしょう。
まとめ

本記事では、窓用エアコンの具体的な電気代と、今日から実践できる5つの節約術、そして根本的な解決策である電力プランの見直しについて解説しました。
窓用エアコンの電気代は、日々の工夫で抑えることも重要ですが、最も効果的なのは電気料金の単価そのものを下げることです。
電力会社を切り替えることで、電気の使い方を変えることなく、無理なく電気代を削減できる可能性があります。
まずは紹介した節約術を試しながら、根本的なコスト削減のために「お得電力」のようなシンプルでわかりやすい電力会社への切り替えを検討してみてください。
<参考>
お得電力