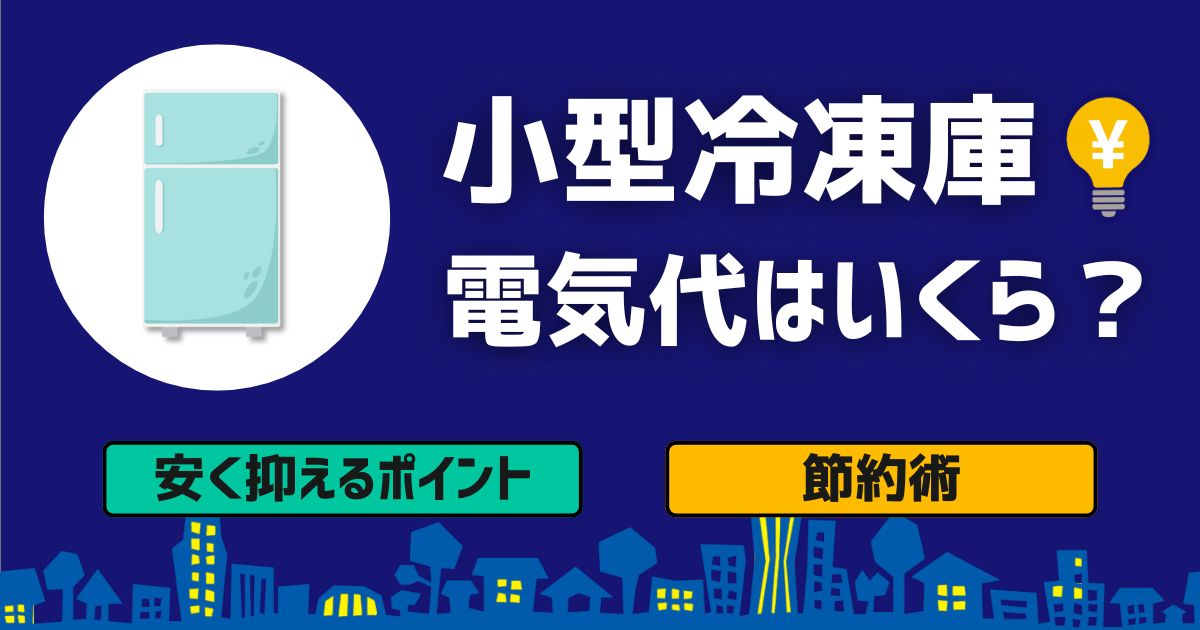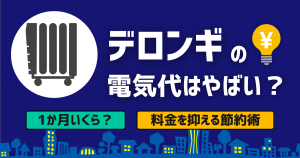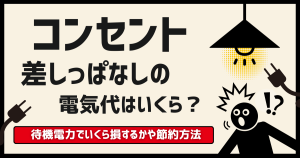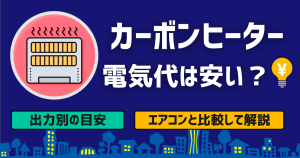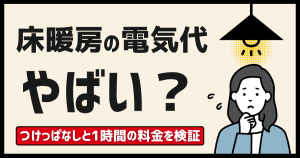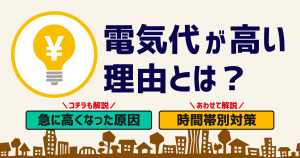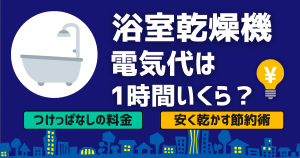まとめ買いや作り置きに便利な小型冷凍庫ですが、購入を検討する際に「電気代がどのくらい上がるのだろう」と心配になる方も多いでしょう。
結論から述べると、製品の選び方や使い方を工夫し、さらに電力契約を見直すことで、小型冷凍庫を導入しつつ電気代を節約できる可能性があります。
本記事では、小型冷凍庫の具体的な電気代の目安から、省エネ性能の高いモデルの選び方、購入後にできる節約術までを網羅的に解説します。
さらに、電気代を根本から見直すためにおすすめの新電力サービスもあわせて紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
小型冷凍庫の電気代は月々いくら?【具体的な料金目安を解説】

まとめ買いや作り置きに便利な小型冷凍庫ですが、新しい家電を増やすことで、家庭の負担が増えるのではないかと心配になる方もいるでしょう。
ここでは、小型冷凍庫の電気代を自身で計算する方法から、容量別の具体的な料金シミュレーション、さらには古いモデルと最新モデルの比較などについて詳しく解説します。
年間消費電力量から電気代を計算する方法
小型冷凍庫の電気代は、製品に表示されている「年間消費電力量(kWh)」を見ることで、自身で簡単に計算できます。
計算式は「年間消費電力量(kWh)× 電力量料金単価(円/kWh)」となります。
電力量料金単価は、契約している電力会社やプランによって異なっており、1kWhあたり27円〜33円程度が一般的な目安です。
たとえば年間消費電力量が200kWhの冷凍庫で、31円/kWhで計算した場合、年間電気代は約6,200円となります。
製品のカタログや本体に貼られているラベルには、年間消費電力量が必ず記載されているため、上記の計算式をもとに購入前に具体的な電気料金をイメージしておきましょう。

【容量別】小型冷凍庫の電気代シミュレーション
小型冷凍庫の電気代が実際にどの程度かかるのか、容量別に見てみましょう。
ここでは、一般的な家庭用モデルを例に、年間の電気代をシミュレーションしました。
| 容量クラス | 年間消費電力量の目安 | 年間電気代の目安 | 月間電気代の目安 |
|---|---|---|---|
| 30Lクラス | 80kWh | 約2,480円 | 約207円 |
| 60Lクラス | 140kWh | 約4,340円 | 約362円 |
| 100Lクラス | 180kWh | 約5,580円 | 約465円 |
このように、比較的小さな30Lクラスであれば月々の負担は数百円程度です。
100Lクラスの大きめなサイズを選んだ場合でも、月々500円以下で利用できるケースが多いと考えられます。
家庭の利用シーンに合わせた容量と、電気代のバランスを比較検討することが大切です。
古いモデルと最新の省エネモデルの電気代比較
現在販売されている小型冷凍庫は、省エネ性能が大きく向上しています。
たとえば、10年前のモデルと最新の省エネ基準を達成したモデルを比較すると、年間の電気代に数千円の差が生まれることも少なくありません。
そのため、10年以上前の古いモデルを使用している場合、最新の省エネモデルに買い替えるのみで、電気代を大幅に節約できる可能性があります。
本体の購入費用はかかりますが、毎月の電気代が安くなることを考慮すると、長期的に見れば買い替えの方が経済的である場合も十分に考えられます。
これから購入を検討する方は、ぜひ最新の省エネ性能に注目してみてください。
電気代が安い小型冷凍庫の選び方【3つの省エネ基準】

小型冷凍庫の電気代を安く抑えるためには、購入時の製品選びが非常に重要です。
省エネ性能の高さを示す指標を正しく理解し、自身のライフスタイルに合ったモデルを選ぶことで、購入後のランニングコストを大きく削減できます。
ここでは、電気代で後悔しないための選び方として、とくに注目すべき3つのポイントを解説します。
省エネ性能を示す「省エネ基準達成率」をチェックする
電気代の安い小型冷凍庫を選ぶ上で最もわかりやすい指標が「省エネ基準達成率」です。
省エネ基準達成率は、製品が国の定めた省エネルギー性能の基準をどれほど達成しているのかをパーセンテージで示したものです。
この数値が100%を超えていれば、基準以上の省エネ性能を備えていることになり、効率の良い運転が期待できます。
ただし、省エネ達成率は消費効率を示す指標であり、電気代そのものを示すものではありません。容量が大きければ、達成率が高くても電気代が高くなるケースもあります。
製品カタログや家電量販店のプライスカードなどに記載されている「統一省エネラベル」には、達成率や年間電気代の目安が記載されています。
デザインや価格のみならず、ラベルを十分に確認し、効率的なモデルを選ぶことが将来の電気代を節約するための重要なポイントとなります。
冷却方式の違い(直冷式・ファン式)と電気代の関係
小型冷凍庫の冷却方式には、主に「直冷式」と「ファン式」の2種類があり、それぞれに特徴があります。
| 冷却方式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 直冷式 | 本体価格や電気代が安い傾向 | 定期的な霜取りが必要 |
| ファン式 | 霜取りが不要で手入れが楽 | 本体価格や電気代がやや高い傾向 |
電気代のみを考えれば直冷式に軍配が上がりますが、数か月に一度の霜取り作業は意外と手間がかかります。
一方、ファン式は自動で霜取りをおこなうため手入れは非常に楽ですが、その分電気代は少し高くなる傾向があります。
電気代の安さを最優先するか、日々の利便性を重視するか、自身のライフスタイルに合わせて最適な方式を選びましょう。
家族構成や用途に合った「適切な容量・サイズ」を選ぶ
小型冷凍庫を選ぶ際に大きすぎるモデルを選んでしまうと、電気代が高くなる原因になります。
冷凍庫は、庫内の中身が少なすぎると冷却効率が落ちてしまうためです。
庫内の食品同士が保冷材の役割を果たすことから、最も効率よく運転できるのは庫内に隙間なく食品が収納されている状態だといわれています。
そのため、まとめ買いの頻度や家族の人数、冷凍したいものの量などを考慮し、家庭に合った適切な容量の製品を選ぶことが無駄な電気代を抑えるうえで非常に重要です。
購入前には、どの程度の量をストックしたいのかを具体的にイメージし、最適なサイズを検討しましょう。
購入後も安心!今日からできる小型冷凍庫の電気代節約術

電気代の安い省エネモデルを選んだ後も、日々の使い方を少し工夫するのみで、さらに電気代を節約することが可能です。
特別なことをする必要はなく、簡単な習慣を心がけるのみで冷却効率を高め、無駄な電力消費を抑えられます。
購入したその日から実践できる効果的な3つの節約術と、さらに一歩進んだ根本的な見直しについて紹介します。
設置場所は壁から隙間をあけ熱源から遠ざける
冷凍庫は、庫内の熱を外に逃がすことで中を冷やしています。
そのため、本体の周囲に十分な放熱スペースがないと冷却効率が著しく低下し、余計な電気代がかかる原因となります。
設置する際は、製品の取扱説明書で推奨されている距離を確認し、必ず壁から適切な隙間をあけるようにしてみてください。
一般的には、背面や側面を10cm以上あけることが推奨されています。
また、直射日光が当たる場所や、ガスコンロといった熱を発するものの近くに置くのも避けるべきです。
外部からの熱は、冷凍庫が庫内を冷やすための負担を増やしてしまうため、設置場所には十分に配慮しましょう。
ドアの開閉時間と回数を最小限に抑える
冷凍庫の電気代を節約するうえで、最も基本的なポイントはドアの開閉をできる限り少なく、そして短時間で済ませることです。
ドアを開けるたびに庫内の冷たい空気は外へ逃げ、代わりに温かい空気が入り込みます。
すると、冷凍庫は再び庫内を設定温度まで冷やすためにコンプレッサーが稼働し、多くの電力を消費してしまいます。
ドアの開閉時間と回数を抑えるためには、冷凍庫の中に何が入っているかを把握し、取り出すものを決めてからドアを開ける習慣をつけることが大切です。
中身が確認しやすいように透明な引き出しケースを活用したり、食材を立てて収納したりする工夫も、開閉時間を短縮するのに有効な方法です。
熱いものは冷ましてから庫内は整理整頓する
調理したものを冷凍保存する際は、必ず粗熱を十分にとってから入れるようにしましょう。
熱いものをそのまま冷凍庫に入れてしまうと、庫内の温度が急激に上昇し、周りの食材を傷める原因になるのみならず、モーターに大きな負担をかけて大量の電力を消費します。
また、冷凍庫は凍った食品が詰まっているほうが冷気が逃げにくく、保冷性が高まるため、電気代の節約にもつながります。
そのため、冷凍庫にはできる限りぎっしりと食品を詰め込みつつ、何がどこにあるのか一目でわかるように整理整頓しておきましょう。
電力会社を切り替えて根本的に電気代を見直す
電気代を根本から見直すためには、契約している電力会社の切り替えが効果的です。
冷凍庫の使い方を変えなくても、電気料金の単価そのものが下がれば、家庭全体の電気代を大きく抑えられる可能性があります。
各電力会社は多様な料金プランを提供しているため、使い方やライフスタイルに合ったプランを選ぶことで、無理のない節約が可能です。
毎月の基本料金や電力量料金を比較し、最適な電力会社を選ぶことが電気代削減への近道になるかもしれません。
次の章では、電力会社の切り替えについて詳しく解説します。
【根本解決】小型冷凍庫の電気代は電力会社の切り替えで安くできる

日々の節約努力も大切ですが、小型冷凍庫の追加で増える電気代の不安を解消する最も効果的な方法は、家庭の電気契約そのものを見直すことです。
電力会社の切り替えと聞くと難しく感じるかもしれませんが、実際には非常に簡単で、電気代を根本から安くできる可能性があります。
ここでは、その仕組みと安心して乗り換えるためのポイントを解説します。
新電力への切り替えで電気料金の単価が下がる
2016年に始まった「電力自由化」により、地域の大手電力会社のみならず、さまざまな企業が提供する電力サービスを自由に選べるようになりました。
電力自由化以降に新しく参入した電力会社は「新電力」と呼ばれています。
新電力は、独自の料金プランやサービスを提供しており、多くの場合、従来の大手電力会社よりも割安な料金設定がされています。
電気代は、主に毎月定額の基本料金と、使用量に応じて変動する電力量料金で構成されているケースが一般的です。
新電力に切り替えることで、とくに電力量料金の単価が安くなる傾向にあり、結果として毎月の電気代節約につながります。
品質の不安を解消するサービスの選び方
大手電力会社から新電力に切り替えたとしても、電気が不安定になったり停電が増えたりする心配はありません。
どの電力会社と契約しても、家庭まで電気を届けるための電線や設備、いわゆる送配電網は、これまで通り地域の大手電力会社のものを共同で利用するからです。
安心して乗り換えるためには、料金プランがシンプルでわかりやすく、企業の運営実績がしっかりしているサービスを選ぶことが重要なポイントといえるでしょう。
おすすめは大手電力会社からそのまま切り替えるだけの「お得電力」
新電力には数多くの企業が参入しているため、どの会社を選べばよいのか迷ってしまう方もいるでしょう。
「複雑なプラン比較は面倒だけど、電気代は確実に安くしたい」と考えている方にはお得電力がおすすめです。
お得電力が最適な理由は、料金プランの圧倒的なシンプルさにあります。
現在契約している大手電力会社の料金プランやサービス内容を一切変えることなく、電気代の請求額のみが安くなるという、非常にわかりやすい仕組みです。
電力会社選びで失敗したくないと考える方にとって、今の生活スタイルを変えずにコストのみを削減できるお得電力は、まさにぴったりの選択肢といえるでしょう。
お得電力が選ばれる3つの理由

小型冷凍庫の導入を検討している方にとって、お得電力が最適な選択肢である理由を次の3つのポイントに絞って具体的に解説します。
- 理由1:大手電力会社より確実に安くなるシンプルな料金体系
- 理由2:電気の品質は変わらず停電リスクも今まで通り
- 理由3:申し込みは最短5分で工事や連絡も不要
電気代への不安を解消し、安心して便利に冷凍庫を使用するために、ぜひ参考にしてみてください。
理由1:大手電力会社より確実に安くなるシンプルな料金体系
お得電力が選ばれる最大の理由は、そのシンプルでわかりやすい料金体系にあります。
お得電力は大手電力会社と同等の料金プランを提供しつつ、基本料金と電力量料金の両方が割安に設定されているため、電気代が安くなります。
たとえば、東京電力エリアの2〜3人世帯の場合、年間で約4,811円、5年間では24,000円以上も電気代がお得になる可能性があります。
全体の電気代が削減されることにより、一般的な小型冷凍庫の年間電気代を十分にカバーできるでしょう。
理由2:電気の品質は変わらず停電リスクも今まで通り
電力会社を切り替える際に多くの方が懸念する、電気の品質や安定供給についても、お得電力ならまったく心配はありません。
前述のとおり、電気はこれまでと同じ大手電力会社の送配電網を利用して家庭に届けられるため、停電のリスクや電気の質は今までと一切変わりません。
また、運営会社である株式会社Qvouは、電力事業のみならず、太陽光発電事業やミネラルウォーター事業など多角的に事業を展開している実績ある企業です。
企業の安定性という側面からも、長期的に安心して契約できるサービスといえるでしょう。
理由3:申し込みは最短5分で工事や連絡も不要
お得電力への切り替え手続きは非常に簡単で、Webサイトから申し込むのみで簡単に手続きが完了します。
Webサイトから最短5分で申し込みが可能で、郵送での煩雑なやり取りは基本的に不要です。
切り替えに伴う工事も一切不要となっており、自宅に作業員が来ることもありません。
さらに、現在契約している電力会社への解約連絡もお得電力が代行するため、自身で連絡する手間がかからない点も嬉しいポイントです。
お得電力の申し込みに必要なものは、毎月の電気使用量や供給地点特定番号などが記載された「検針票」のみです。
このように申し込み手続きは非常に簡単であるため、忙しい毎日を送る方や、手続きが面倒で行動に移せなかった方にもおすすめです。
小型冷凍庫の電気代に関するよくある質問(FAQ)

小型冷凍庫の電気代や選び方に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。
購入前の最終確認として、ぜひ参考にしてみてください。
セカンド冷凍庫を置くときの注意点はありますか
セカンド冷凍庫としてリビングや寝室などに置く場合は、電気代のみならず運転音の大きさも確認することが重要です。
運転音はdB(デシベル)という単位で示され、数値が小さいほど静かになります。
一般的に30dB以下であれば、非常に静かだと感じられるでしょう。
また、設置スペースを有効活用したい場合は、天板が熱に強い「耐熱トップテーブル」仕様のモデルがおすすめです。
このタイプであれば、冷凍庫の上に電子レンジやオーブントースターなどを置くことができるため、キッチンスペースが限られている家庭でも重宝します。
設置場所の寸法とあわせて、上記の点もチェックしておくと安心です。
霜取り不要のファン式は本当に電気代が高いのですか
一般的に、ファン式の冷凍庫はヒーターを用いて自動で霜取りをおこなうため、その機能がない直冷式に比べて電気代が高くなる傾向にあります。
しかし、近年は省エネ技術が大きく進歩しており、両者の電気代の差は以前よりも小さくなってきました。
また、直冷式は霜が分厚く付着すると冷却効率が著しく低下し、かえって電気代が高くなることがあります。
定期的な霜取りの手間や冷却効率の維持を考慮すると、多少電気代が高くてもファン式を選んだ方が総合的な満足度や利便性が高いかもしれません。
それぞれの特性を理解し、自身の使い方に合った方を選ぶことが大切です。
電気代以外にチェックすべき冷凍庫の機能はありますか
電気代以外でチェックしておきたい機能として、まず急速冷凍機能が挙げられます。
急速冷凍機能を使用すれば、食材の細胞破壊を抑えながら素早く凍らせることができるため、解凍した際のおいしさや食感を保ちやすくなります。
また、庫内の引き出しやケースの仕様も重要です。
中身が見やすい透明なケースや、整理しやすい仕切りが付いているモデルは、食品ロスを減らし、ドアの開閉時間を短縮するのにも役立ちます。
さらに、設置場所によってはドアの開閉方向が使い勝手を大きく左右します。
壁の位置にあわせて、右開き、左開き、あるいは上開きの中から、スムーズに出し入れできるモデルを選びましょう。
まとめ:小型冷凍庫の電気代は選び方と契約見直しで賢く節約

本記事では、小型冷凍庫の電気代に関する具体的な料金目安や選び方、そして日々の節約術について解説しました。
電気代を安く抑えるためには、省エネ性能の高いモデルを選び、適切な使い方をすることが基本です。
しかし、最も効果的な解決策は、電気の契約そのものを見直すことにあります。
冷凍庫一台の電気代を気にするよりも、家庭の電気代全体が安くなれば、安心して便利な家電を暮らしに取り入れることが可能です。
とくに、お得電力のように今の使い方を変えずに料金のみを安くできるサービスは、失敗したくない方にとって最適な選択肢となるでしょう。
本記事で得た知識をもとに、自身のライフスタイルに合った最良の選択をし、節約と利便性を両立させた豊かな毎日を送ってください。
<参考>
お得電力